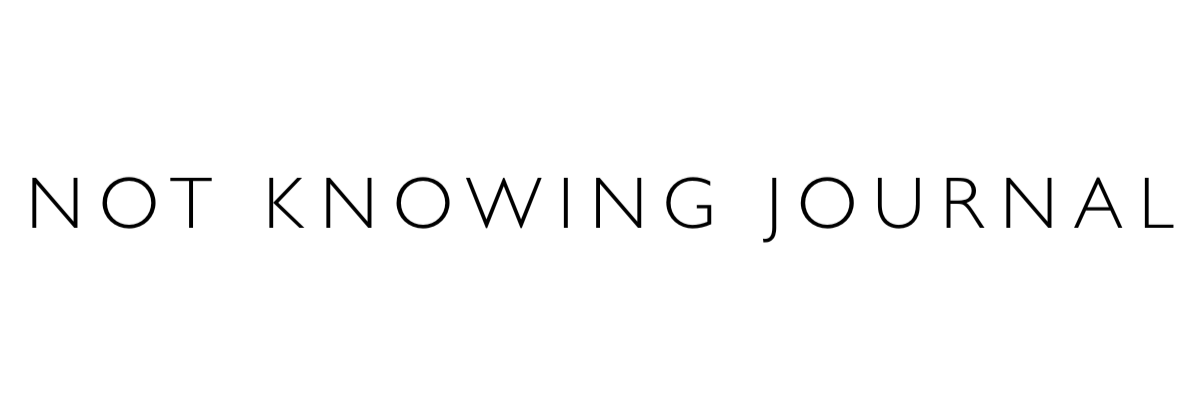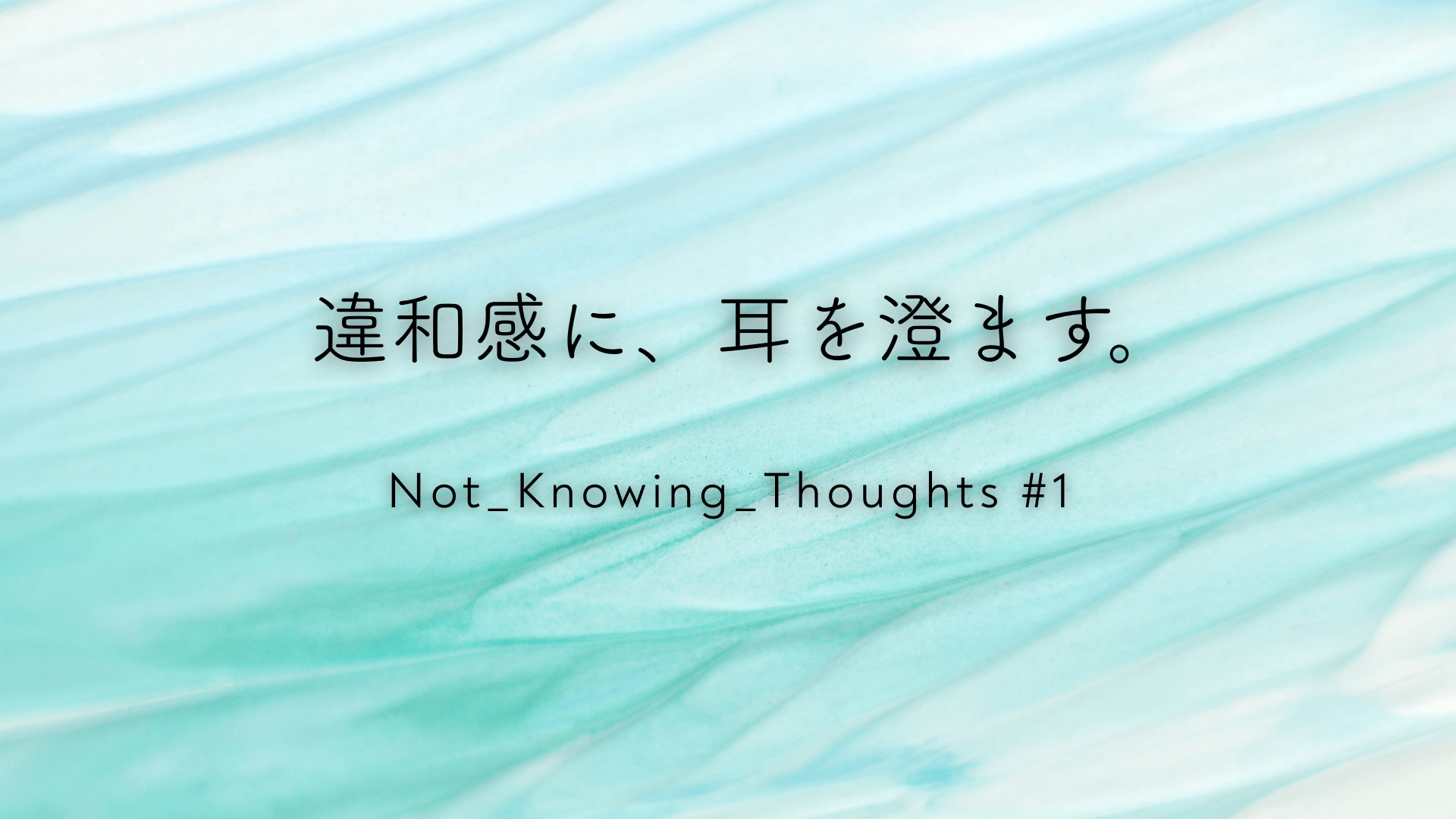ある日、何気なく見ていたサイトで、路面電車と自動車の衝突事故が報じられていました。
そのニュースに対するネット上の声を見てみると、「自動車が悪い」「ルールを知らずに車を運転するな」といったものばかり。
けれど、ぼくはその光景に、ある違和感を覚えました。
——なぜ、路面電車の存在そのものを問う声が、まったく存在しないのだろう?
これは、路面電車の是非を問いたいという話ではありません。
“根本的な問い”や“俯瞰してみる視点”が、まったく存在していない点が気になったのです。
たとえば、「なぜこの都市に路面電車が必要なのか」「自動車と共存するインフラとは何か」といった視座の広い議論が、どこにも見当たりませんでした。
深い思慮の果てにたどり着いた結論であれば、たとえそれが多数派であっても問題はない。
しかしそこには、そもそも思考する姿勢自体が欠けているように感じられたのです。
この小さな違和感をきっかけに、ぼくは三木清やハンナ・アーレントといった思想家たちの言葉を思い出しました。
現代に生きるぼくたちは、もしかすると、自分でも気づかぬうちに“当たり前”の奥にある問いを見失い、沈黙のうちに思考を手放しているのかもしれません。
この記事では、そんなぼく自身の実感から、「考えることとは何か」をあらためて問い直してみたいと思います。
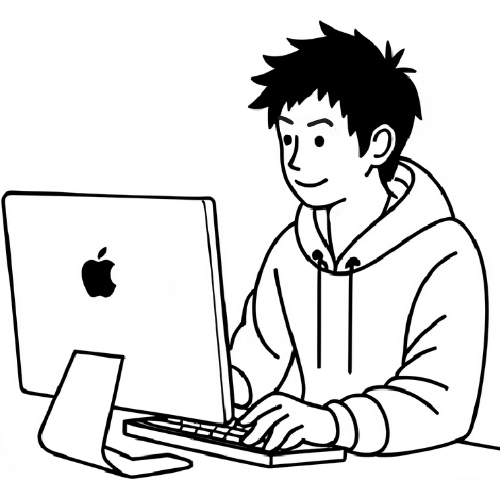
この記事を書いた人
ヒラク
NOT KNOWING JOURNAL 運営・執筆
早稲田大学 政治経済学部 政治学科
→ 総合医療機器メーカー
→ フリーランス
ある事故報道を見て覚えた「違和感」

路面電車と自動車の衝突事故——なぜ自動車だけが責められるのか?
ある日、ネットニュースで一件の事故報道を目にした。
「路面電車と自動車が交差点で衝突。自動車を運転していた男性が搬送され、運行に遅延が発生」。よくある事故報道のひとつに見えた。
しかし、その投稿のコメント欄を読み進めるうち、奇妙な感覚に襲われた。
「自動車が悪いに決まってる」「運転手はちゃんと確認して運転しろ」「また右折車かよ」——そうした声が並び、路面電車側を非難する声はひとつとして見当たらなかった。
その反応にぼくは、具体的な違和感よりも、“違和感が存在しないこと”に対する違和感を覚えたのだ。
なぜ誰も、路面電車の運行体制や走行の優先権、またそもそも都市のなかを“軌道に縛られた車両”が走るという構造自体に目を向けないのだろうか。
まるで自動車の過失を断じることが「正解」となっており、それ以外の可能性を思考の外に押し出してしまっているようだった。
たしかに、多くの都市で路面電車には優先権がある。
だが、それは法律や交通ルールの話であって、「本当にそれでよいのか」という問いを封じる理由にはならないはずだ。
ぼくはこの瞬間、自動車が悪いという意見そのものではなく、その前提にある “思慮の不在” に深く引っかかったのである。
なぜ誰も“路面電車の存在”そのものを疑わないのか
なぜ自動車側の不注意ばかりが問われ、路面電車が街の中を走っていることについては誰も考えようとしないのだろうか。
もちろん、すべての人が無思考なわけではない。だがこの社会の「空気」は、路面電車という存在を疑うことすら“ナンセンス”だとみなしているように感じる。
それは、議論や異論がないというよりも、議論が起こりうるという発想そのものが存在していない状態なのだ。
路面電車は「公共交通」であり「エコ」であり、さらに「都市の文化資産」でもあるとされている。
だがその一方で、自動車等に比べ、自由な動きを制限された鉄の塊が、歩行者や車のすぐ脇を走っている現実が、どれだけの危険や不自由を内包しているか。
それに目を向ける視点が、あまりにも希薄ではないだろうか。
ここでぼくが問いたいのは、単に路面電車の是非ではない。
路面電車の存在という「当たり前」が、ぼくたちの思考を麻痺させてはいないかということだ。
ぼくたちは今、資本主義という巨大なシステムのなかで、「効率的であること」「合理的であること」に価値の基準を置いている。
そしてそれが、時として人間生活におけるバランスを考慮しない事態を生み出している。
効率性ももちろん大事だ。けれど、今の時代はその効率性が、もはや聖域となっている。
簡単に自動車の運転手を断罪して終わりにするのは簡単だ。けれど、世の中には運転の上手でない人・ルールをよく把握していない人だって現実にいる。きれいごとだけで割り切れないのが、世の中の現実なのだ。
路面電車は、定刻で運行され、交通渋滞にも左右されず、都市機能を円滑に回す手段として長く評価されてきた。
だがその「効率」の裏には、立ち止まって考える余白が、あまりにもない。
むしろ、立ち止まること自体が“非効率”だと退けられてしまう。
この事故をめぐる反応は、単なる交通トラブルではなく、ぼくたちの精神がすでに「効率」という名の自動運転モードに入り込んでしまっていることを、暗黙のうちに示していたのではないだろうか。
「精神のオートマティズム」とは何か——三木清が指摘した思考の惰性

三木清が語る「考えること」とは、自明性を問い直すこと
この「当たり前」に飲み込まれた感覚は、三木清の言葉によって照らされる。彼は『人生論ノート』のなかで、「考える」とは“自明と思われていることを問い直す行為” だと述べている。つまり、「なぜそうなっているのか」「それは本当に正しいのか」といった根源的な問いかけこそが、思考の出発点だというのだ。
だがぼくたちは、多くの場合、この“問い直し”をしない。制度も慣習も、「そういうものだから」という理由で受け入れてしまう。それが三木清の言う「精神のオートマティズム」——思考の惰性である。
このオートマティズムとは、思考している「つもり」で、実際には思考を放棄している状態だ。目の前の現象を、自分の経験や社会の通念でそのまま解釈し、それ以上踏み込まない。いや、踏み込むことを思いつきもしない。言い換えれば、“当たり前”の座標軸で世界を眺めることに、無自覚に慣れてしまっているのだ。
このような精神の自動運転状態に陥ると、ものごとの深層にある構造や力学には気づかなくなる。冒頭の「路面電車と自動車の事故」をめぐる反応も、まさにその典型だと感じた。
私たちは、何を“自動的に”受け入れているのか
こうしたオートマティズムに支配されているのは、交通インフラに限らない。ぼくたちは日々、さまざまなものを“当たり前”として受け入れている。たとえば、学校に通うこと、会社に勤めること、お金を稼いで生活すること。それ自体が悪いわけではない。だが、その根底にある仕組みや価値観を“問うこと”すらしないのなら、それは「思考」ではなく「順応」に過ぎない。
そして、問い直されない「当たり前」は、いつしか「問うことを許さない空気」へと変質していく。たとえば「路面電車は環境にやさしい」「都市交通の要である」といった言説は、それが真実であるか否かにかかわらず、語られることが正義とされ、疑うこと自体がタブーとなる。このようにして、ぼくたちは思考を停止したまま、「常識」という名の力学 に取り込まれてゆく。
加えて、そこにはもう一つの側面がある。すなわち、「効率」や「生産性」を絶対視する 資本主義的価値観の支配 である。都市における路面電車の存在は、環境配慮や交通インフラという名のもとに、美名で装飾されているが、それは本当に人間の安全と自由のためのものなのか。路面電車のために交通を止め、自動車を制限し、事故が起きた際にも「前提」として非を問われない構造。それはまさに、人間の営みよりも「システム」の効率を優先している のではないか。
ぼくたちはいま、「人間が仕組みに従う」という逆転した価値観のなかにいる。そのことに気づき、少しでも立ち止まること。三木清の言葉を借りるなら、それが「本当に考える」ということなのだ。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
ハンナ・アーレントが描いた「考えないこと」の恐ろしさ

ナチスのアイヒマン裁判と「凡庸な悪」
「思考を放棄することが、人を悪に向かわせる」。
ハンナ・アーレントがこの洞察に至ったのは、1961年に行われたナチス戦犯アドルフ・アイヒマンの裁判を傍聴したことがきっかけだった。
アーレントは当初、ユダヤ人迫害の責任者としてのアイヒマンに、冷酷で異常な悪魔性を期待していた。だが実際に法廷に立った彼は、ごく普通の官僚のように見えた。平凡な中年男性が、命令に忠実に従っただけだと淡々と語る姿に、彼女は衝撃を受けた。
彼は考えていなかった——
命令を遂行することに忠実であるがゆえに、何が善で何が悪か、自らの行動がもたらす帰結について、彼は一切思考していなかった。
アーレントは、これを「凡庸な悪」と呼んだ。悪は、サディスティックな悪人によってだけではなく、“思考停止”の中で生まれうるのだという警鐘である。
この指摘は、歴史の教訓として、現代に生きるぼくたちにも重くのしかかってくる。
「政治不信」と「思考の放棄」は、現代の私たちを侵食している
現在の日本では、物価の高騰やリーダーシップの不在などにより、政治に対する不信感・社会に対する不満は極めて高い状態にあると言える。こうした状況で、そうした不信・不満をうまく煽り立てるような指導者が登場すれば、その社会に全体主義をもたらす——これは空想でもなんでもなく、歴史が証明していることだ。
「政治不信」が「思考の放棄」へと変わったとき、ぼくたちはこうつぶやく——
「どうせ変わらないから」「誰がやっても同じだろう」
こうした言葉が口をついて出るとき、ぼくたちは完全に、思考することを放棄している。そしてその放棄は、制度への無条件な服従へとすり替わっていく。
ここで言う「服従」は、暴力的な圧力によるものではない。むしろ、社会の空気、同調圧力、あるいは「無関心」という名の沈黙の中で、徐々に進行していく。
ぼくたちはアイヒマンではない。だが、アーレントが指摘した「考えないことがもたらす凡庸な悪」は、ぼくらのすぐ足元にも潜んでいる。
「疑うこと」や「考え直すこと」は、特別な能力ではなく、日常における小さな姿勢の問題である。「当たり前」の中に潜む危うさに目を向けること。それが、ぼくたちが社会の構成員として担うべき、ささやかだが重要な責任ではないだろうか。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
思考停止が招く社会の“静かな息苦しさ”

民主主義も、資本主義も、「仕組み」ではなく「向き合い方」が大切
ぼくたちは、しばしば「民主主義だから」「資本主義だから」と、制度や仕組みそのものに意味を見出し、それを疑うことなく信奉してしまう。だが本来、それらは人間が社会を円滑に運営するために編み出した道具に過ぎない。仕組みは目的ではなく、手段であるはずだ。
資本主義の論理においては、効率と利便性が最優先される。都市のインフラ、交通の設計、流通、労働環境に至るまで、その根底には「より速く、より多く、より合理的に」という価値観が通奏低音のように流れている。だが、それが人間の「安全」や「尊厳」を脇に置いてまで優先されるようになったとき、そこには本末転倒の危うさが生まれる。
路面電車の話に戻ろう。都市の中心を走るこの乗り物は、公共交通としての歴史的価値や環境面でのメリットが語られる一方で、自動車との交錯による危険性には十分に光が当たっていないように思える。「路面電車があって当たり前」という前提を疑わないこと。それは、資本主義的な利便性の論理が、いつのまにか 人間の思考そのものを上書きしている証 ではないか。
民主主義についても同様だ。「選挙で選ばれているのだから正当だ」「手続きが守られているのだから問題ない」——こうした考えの裏には、制度の正当性を問うことへの遠慮がある。けれども本来の民主主義とは、制度の中で思考を止めず、異議を唱え、問い直す自由を市民が手放さない ことにこそ、その本質があるはずだ。
つまり、制度や仕組みが悪いのではない。それらとどう向き合うのか、自らの感覚と知性でどう問い続けるか——その姿勢の有無が、社会の息苦しさをつくり出すか、それとも風通しを保つかの分かれ目になるのだ。
違和感を抱く感性を、大切にしたい
思考停止は、必ずしも暴力的なかたちで社会を支配するわけではない。むしろ静かに、穏やかに、そして無自覚に人々の心を蝕んでいく。それは “静かな息苦しさ” として、ぼくたちの内側に溜まり、問いを立てる力を鈍らせていく。
だからこそ、ぼくらは「違和感」という感覚をもっと信じてよい、と思う。それは理屈ではない。説明できないけれど何かがおかしい、何かが見過ごされている、そう感じる感性——それこそが、思考停止から抜け出す最初の扉 である。
問いは大きくなくてもいい。制度や社会全体を変える必要もない。ただ、「本当にこれでいいのだろうか」と一度立ち止まってみること。それが、他者の声に耳を傾けるきっかけになり、自分自身の目で世界を見つめ直す原点となる。
社会を大きく変えるのは、声高な主張や激しい行動ではなく、小さな違和感に忠実であろうとする日々の姿勢 かもしれない。都市を行き交う電車や自動車の音のなかで、ふと立ち止まれる自分でありたい。
まとめ——「当たり前」にこそ、問いを

ぼくたちの暮らしは、「前提」に満ちています。
道路のつくり、交通ルール、組織のあり方、働き方。そうしたものが、当然のものとして、疑われることなく、日々を流れていきます。
けれども、その「当たり前」は、誰かが作ったものです。過去の制度設計、権力構造、経済の論理——それらが編み込まれてできた「仕組み」です。そしてぼくたちは、その仕組みによって守られながらも、同時に、縛られてもいます。
思考の惰性に身を委ねることは、たしかに楽です。空気を読み、同調することで争いは避けられ、効率も上がるでしょう。しかし、それだけで社会を前に進めることはできません。
「なぜ、そうなのか?」
たったひとつの問いが、風通しのよい社会をつくる第一歩になるはずです。
今回の路面電車の事故報道で、ぼくはそのことをあらためて実感しました。
自動車の責任を問う前に、そもそもなぜそこに路面電車があるのか——誰もが見過ごしている前提に目を向けること。それが「考える」という営みの始まりなのだと思います。
ぼくたちは、もっと自由に問いを立てていい。
たとえ小さな違和感であっても、それを無視せず、言葉にし、誰かと共有すること。
その積み重ねが、「仕組み」に飲み込まれない生き方を育てていく。
そして、一人ひとりの精神の自由を守ることにつながるのだと、ぼくは信じています。
📬 ことばが、どこかであなたに触れたなら──
小さな便りをお寄せいただけたら、とても励みになります。