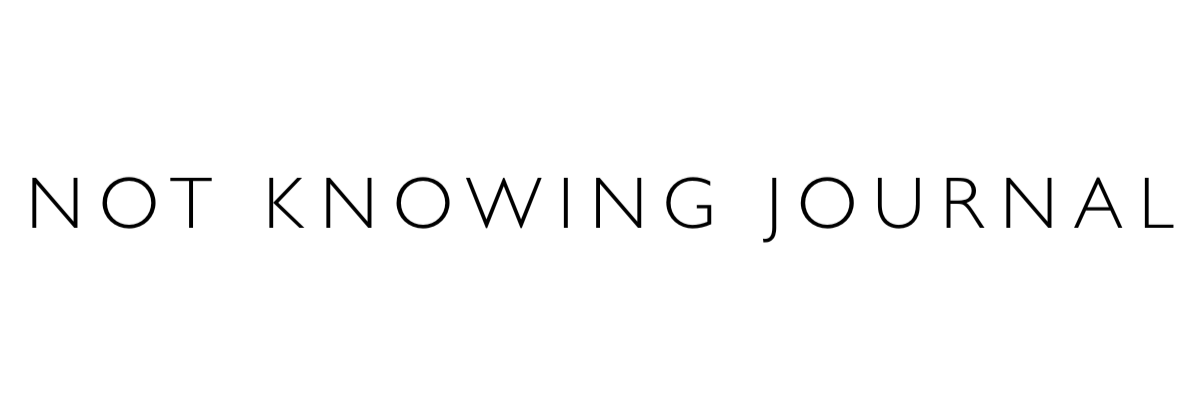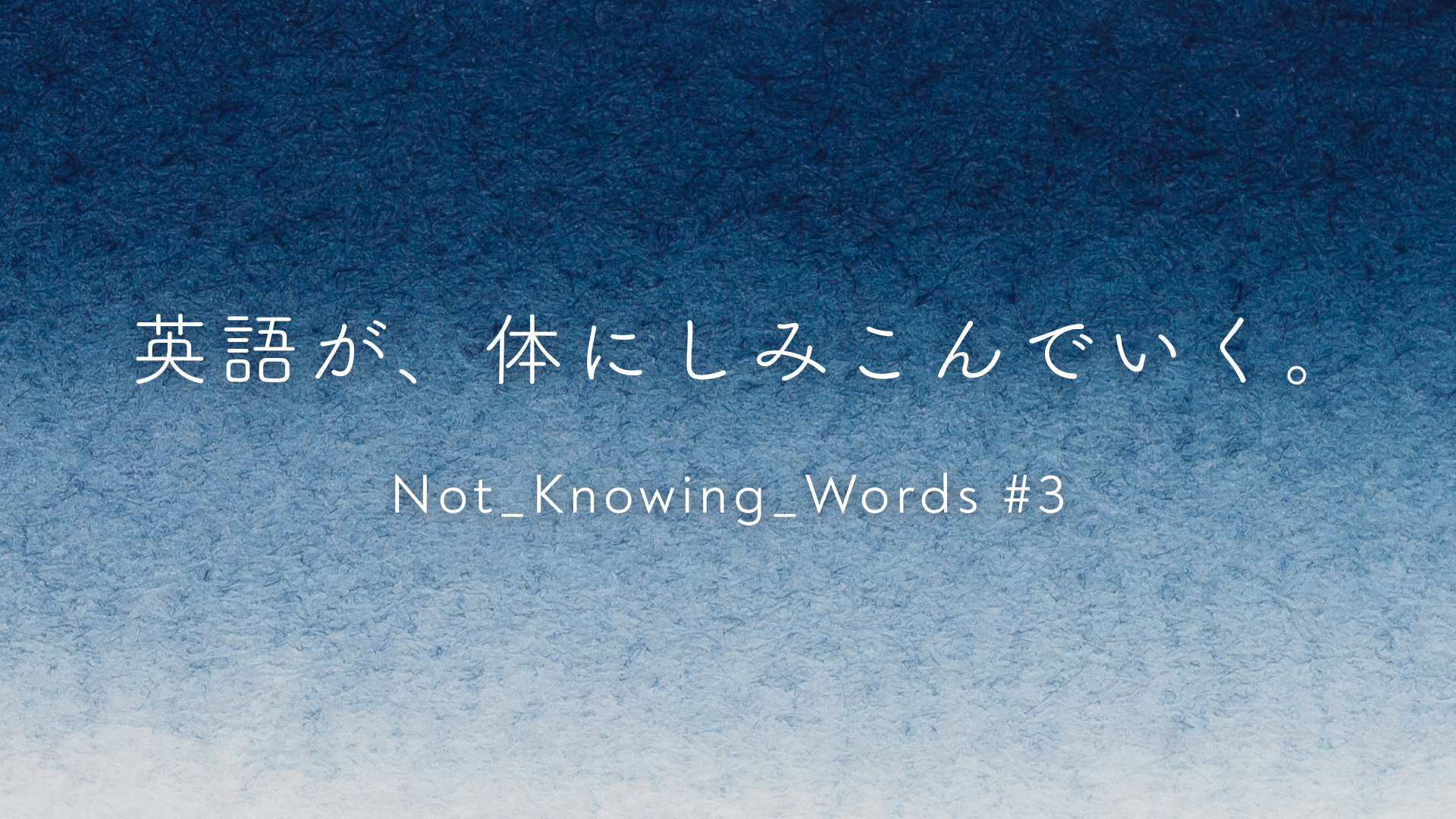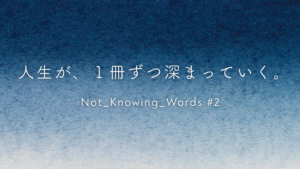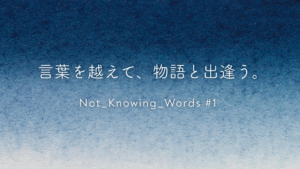英語を勉強していると、「なんとなく、こうすれば上達するんじゃないか」っていう、ぼんやりとした感覚がふと湧いてくることがあります。
ぼくにも、そんな小さな気づきがありました。でも、それが何なのか、はっきりとはわからないまま、ずっと胸の奥でつかみ切れずにいました。
そんなとき出会ったのが、國弘正雄さんの本でした。ページをめくるたびに、「ああ、これだ」と思わされる。言葉にならなかった感覚が、國弘さんの言葉によって、少しずつ形を持ちはじめる。自分の中にあった曖昧な思いが、静かに結晶化していくような体験でした。
英語の学び方は人それぞれ。でも、自分にとってしっくりくるやり方って、たしかにあるんだと思います。
國弘さんの本を読んでから、ぼくは周りの声ではなく、自分の感覚を大切にするようになりました。
この記事では、國弘正雄さんの著書『國弘流 英語の話しかた』をもとに、ぼくの学習体験も紐解きつつ、日本人に最適な英語学習法について考えてみたいと思います。
英語学習のヒントを探している方にとって、少しでも参考になればうれしいです。
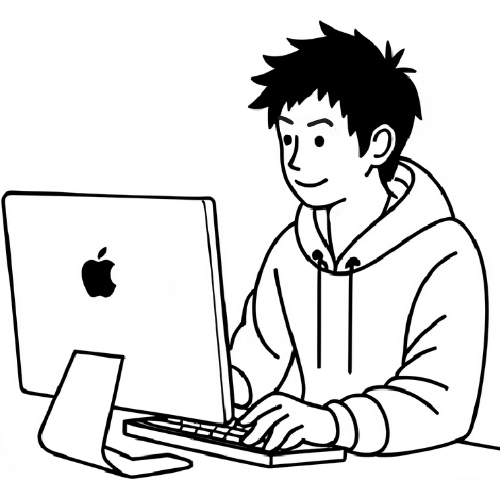
この記事を書いた人
ヒラク
NOT KNOWING JOURNAL 運営・執筆
早稲田大学 政治経済学部 政治学科
→ 総合医療機器メーカー
→ フリーランス
同時通訳の神様・國弘正雄ってこんな人
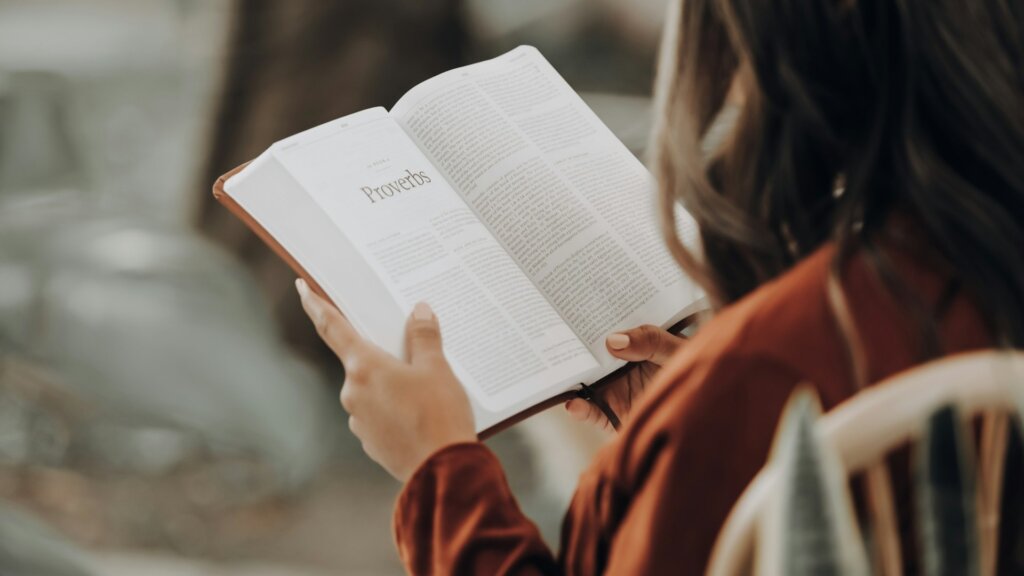
國弘正雄:経歴

昭和5年(1930年)8月18日 ▶ 東京都北区生まれ
昭和30年(1955年)▶ ハワイ大学卒業、卒業後は日本のシンクタンクのアメリカ常駐スタッフとして勤務
昭和39年(1964年)▶ 中央大学法学部専任講師(文化人類学)
昭和40年(1965年)▶ NHK教育テレビ「英語会話中級」講師
昭和53年(1978年)▶ 日本テレビと専属契約を締結、多数の番組に出演
平成元年(1989年)▶ 参議院選挙に日本社会党より立候補、当選
平成12年(2000年)▶ 勲三等旭日中綬章受章
平成26年(2014年)11月25日 ▶ 老衰のため死去、84歳
英語界における足跡
- 英語学習者として…
-
- 中学生のとき、新渡戸稲造 の伝記に影響を受け、英語の勉強を開始。
- 日本に進駐していた各国の兵士に英語教科書に載っている英文の発音を尋ね、それを参考にひたすら音読を繰り返した。
- 英語実務家として…
-
- アポロ11号の月面着陸を伝える生中継に同時通訳者として出演。のちに「同時通訳の神様」と呼ばれるようになった。
- 音声通訳のみならず、翻訳家としても活動。
- 英語教育者として…
-
- NHKにて英語教育番組の講師を務めたほか、トーク番組に海外の著名人を招き、豊富な知見・圧倒的な英語力を披露している。
- 英語学習に関する書籍を多数執筆。その多くは英語初心者向けのもの。
『國弘流英語の話しかた』から見えてくる英語学習の真髄

只管朗読:黙って朗読せよ、ひたすら朗読せよ
『國弘流英語の話しかた』に書かれていることは、たったひとつの言葉に集約できます。
それは、只管朗読(しかんろうどく)——。
仏教、なかでも禅宗に「只管打坐(しかんたざ)」という言葉があります。「余計なことは考えず、ただ座る」。その精神を、英語学習に転用したのがこの【只管朗読】という言葉なのです。
意味は、シンプル—— ただ、ひたすらに英文を朗読すること。
頭でこね回さず、技術を追い求めず、評価を気にせず、ただ声に出して読む——その姿勢が、國弘さんの言う英語との誠実な向き合い方です。
繰り返すことの重要性
英文をただ読む。
これほど単純な方法が、果たして効果的なのか。
多くの人がそう疑問を抱くでしょう。けれど國弘さんは、そこにこそ本質があると説きます。彼が語るポイントは、ふたつ。
ひとつ目は、意味を理解した上で読むこと。ふたつ目は、その素材を徹底的に繰り返すこと。
ここでは後者、「繰り返すこと」の価値に焦点を当ててみたいと思います。
なぜ同じ英文を、飽きるほど読む必要があるのか。
その問いに対し、國弘さんは芸術や音楽といった異分野のプロたちの言葉を引き合いに出して語ります。
たとえば、ヴァイオリニスト・諏訪内晶子さんのこんな言葉——
壁はいくつもあるけれど、同じ曲を何十回、何百回と弾きつづける中で、突然パアーッと青空が開けたような瞬間がくる。その時、自分の力が一段と飛躍した感覚になって、面白くてたまらなくなりますね。
引用元:國弘流英語の話しかた
繰り返すことでしか辿り着けない風景がある。ある日、突然。霧が晴れたように世界が開ける ——
ぼく自身も、受験生時代にこの感覚を体験しました。英文を繰り返し音読し続けるうち、あるときから突然、英語が英語のまま理解できるようになったのです。
英語が面白くてたまらなくなり、成績も一気に伸びていきました。
もちろん、受験英語という限定された枠の中での話です。
それでも確かに感じたのは、「繰り返し」だけが連れていってくれる場所がある、ということです。
國弘さんは「繰り返すこと」について、こんなふうに語っています。
同じことを繰り返すなんて、飽きてしまって、時間の無駄だと考えるのは、ごく普通だと私も思いますが、そこを飽きない人が飛躍するのです。なぜ、彼らは飽きないのか。それは、ここに紹介した人々のファイルを読めばおわかりでしょう。
はた目には単調な繰り返しに見えても、当人たちは、技術の奥行き、質の深化ということを生き生きと感じているのです。それに惹かれて、繰り返せるのです。まさに彼らにとって、繰り返しは無限の喜びなのです。
引用元:國弘流英語の話しかた
飽きない者が、飛躍する。
その鍵は、表層をなぞるのではなく、奥行き と 深み を感受できるかどうか。
ただ同じことを繰り返しているように見えて、その中にささやかな変化を感じ取ることができるかどうか。
國弘さん自身、中学時代に教科書をほぼ丸暗記するまで朗読を繰り返したと言います。それが、彼の英語力の原点であったと。
繰り返しのなかに、言葉の手触りを見出せるか。
その繰り返しが「無限の喜び」へと変わるかどうかは、まず「繰り返し」に向き合う姿勢 が大切なのだと思います。
只管朗読と英文法
本書では、英文法についても言及されています。
「文法ばかりやっているから日本人は英語が話せない」—— そうした通説に対し、國弘さんは明快に異を唱えます。
日本人は文法、文法と言うから英語が出来ないのだと、久しく言われ続け、現在も盛んに言われているようですが、事実は全く逆で「まだまだ文法の勉強が足りない」というのが真相 のようです。文法の理屈や文法用語の暗記が足りないのではありません。訓練が足りない のです。
引用元:國弘流英語の話しかた
この「訓練」という言葉は、まさに只管朗読のことを指しています。
文法は知識ではなく、体得すべきもの。理解と記憶だけでは不十分で、「繰り返し」によって身体に染みこませる必要がある——。これが國弘さんの立場です。
言い換えれば、「抽象」と「具体」のバランスの問題です。
文法という “抽象” を知ったあとに、それを “具体” の英文の中で繰り返し体験する。
わからなくなればまた抽象に立ち返る。行きつ戻りつしながら、理解を深めていく。
このような学びの方法は、実は古くから日本の教育文化に根付いていたものです。
たとえば江戸時代の寺子屋では、漢文の素読が盛んに行われていました。まずは読み、身体に沁み込ませる。その後で意味を理解していく。
また、数学の世界でも同様の手法が用いられてきました。
数学者・森田真生さんは、日本独自の数学術「和算」について、次のように記しています。
たとえば江戸時代の日本には、「和算」という独自の数学文化があった。
そこでは、まっしぐらに抽象化・普遍化に向かわずに、特殊な設定下の具体的な例を数多く身に付けることを通して、背景ではたらく原理を少しずつ「悟っていく」ような学習法・教授法が重視された という。
和算には、西欧近代数学とは異なる数学の美意識と価値観があったのだ。
引用元:『数学する身体』森田真生
まさに、「具体の積み重ねを通じて、抽象を “悟る” 」という道。
これこそ、日本人の精神土壌に根ざした学びの姿勢なのかもしれません。
ぼくたちは英語ができない理由を「学校英語が悪いから」と断じ、教育制度を何度もいじってきました。けれど、その結果、英語力が高まったとは言えません。
目新しいノウハウや “ラクなやり方” に惑わされるよりも、原点に立ち返るべきではないでしょうか。
ただ読む。ただ繰り返す。ただ声に出す。
【只管朗読】という行為は、ぼくたちが見失っていた “誠実な学び” そのものです。
静かに、深く、自分自身の声と響きを聴きながら英語と向き合う時間は、英語という言葉と一体になるための地味だけれど、確実な方法だと思います。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
國弘正雄が唱える只管朗読:取り組み方とその効果
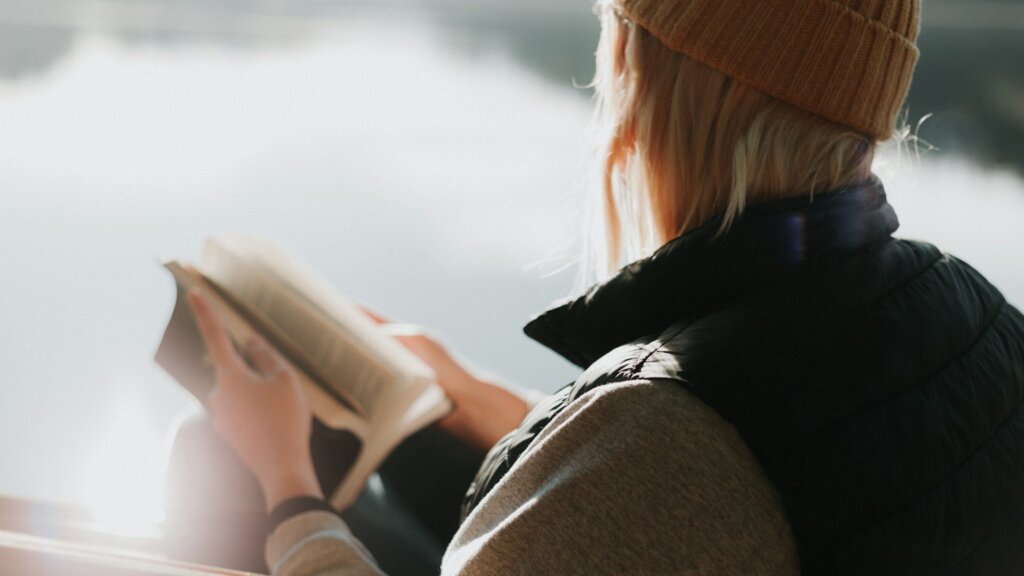
音読素材の選び方
只管朗読の取り組み方として、まずはじめに音読素材の選び方を取り上げます。
素材を選ぶときに絶対に外せない条件は、【①意味を理解した英文であること】です。
たとえばぼくは、受験生のころから、音読素材にした英語長文の単語を一つ一つ調べ、構文を読み解き、日本語訳をとることを続けてきました。
それは当たり前の作業として、迷うことなくやってきましたが、なぜそこまで深く意味を理解しておく必要があるのか、と問われれば、はっきりと答えられなかったのも正直なところです。
ところが國弘さんは、この点を明快に言葉にしてくれています。
音読は、意味を理解することや知識を得ることを目的にしているわけではありません。
意味理解は、音読という旅を始めるための出発点ですらなく、その前提として済ませておくべきものなのです。
もしあなたが高校生なら、易しい中学レベルの英文で意味を掴んでから進むのもいいでしょう。
ぼくのように、大学受験レベルの英文を構文まで解釈してから読み始めるのもまた、正しいやり方です。
社会人の方で、構文の解き方を忘れてしまったり、単語を調べる時間が取れなかったりするなら、初めて見てすぐ理解できるレベルの英文を選べばいいのです。
意味理解の仕方や深さについては、國弘さんの言葉を借りておきます。
英文の意味を一通り理解するにはどうしたらよいかという質問は当然です。よさそうな手段はなんでもお使いください。辞書で単語の意味を調べること。日本語の訳を教えてもらうこと。その訳も、意訳・直訳・文頭からの便法訳と、何をどう使っても結構。主語・目的語・修飾語と文の構造分析 も遠慮せずにおやりなさい。(中略)
確かに分析魔の悪しき傾向というものはあります。分析するばかりで総合がないことです。何事も分解のしっぱなしはいけません。総合を音読でやるのです。只管朗読には分析毒の解毒作用もあるのです。
引用元:國弘流英語の話しかた
「総合を音読でやる」という言葉には、音読を経験した人なら誰もが心を動かされるはずです。
意味理解の段階で英文をパーツに分解し、音読でそれをまた一つにまとめていく。
まるで機械好きの少年が、分解し組み立て直すことで機械の構造を体で理解するように。
取り扱い説明書を読むだけでは、肌感覚は得られない。
だから、声に出して【分解→総合】するプロセスが欠かせないのです。
教材の難易度や分量についても、國弘さんは触れています。
短い会話文だけのものはおすすめ出来ません。やはり、単語の点でも、文の構造の点でも、基礎的なものが一通り出てくるような教材 が望ましいのです。
長いものは繰り返すことが出来ません。繰り返さなくては成果は上がりません。
引用元:國弘流英語の話しかた
この点についても、ぼくの考えは同じです。
会話文だけのものを避けるという意味では、ノンフィクションを中心に読むのが良いでしょう。
また、長すぎると繰り返すことができない一方で、短すぎるとパターンを刻むだけの負荷になりません。
ぼくの場合は、英語の長文問題1~2ページ(洋書であれば文字が小さいので1ページ)程度を目安に取り組んでいます。
さて、意味理解というハードルを越えたその先で、音読はぼくたちに何をもたらすのでしょうか。
音読がもたらす効果
國弘さんは音読の5つの効果を挙げていますが、その中からぼく自身が深く実感した3つを紹介します。
- 直読直解が可能になる
- 有意義な多読が可能になる
- 難しい英語に取り組む力がつく
直読直解が可能になる
直読直解とは、英語を英語のままに理解することです。
初めのうちは「英語を読んで→日本語に置き換えて→意味をつかむ」という順序を踏みます。
しかし、只管朗読を積み重ねるうちに、その壁は徐々に取り払われていきます。
日本語に翻訳せずとも、英文の語順そのままに、意味をつかめるようになるのです。
國弘さんはこう記しています。
英語をひたすら音読することによって、英語の語順どおりに意味をとっていくという思考パタンが脳の中に深く刻まれるのです。いったんそのパタンが刻まれればしめたものです。おなじパタンに出くわせば、直ちに文頭からそのまま読んで意味がわかります。
引用元:國弘流英語の話しかた
ここで大切なのは、「パターンが脳に刻まれる」ということ。
ぼくはこの状態を、「英語理解のための枠組みが脳内にインストールされる」と表現します。
パソコンに例えれば、OS が人間の入力情報を正しく処理するのと同じように、脳の中に、英語の文字や音声を正しく処理し、意味を瞬時に理解する司令塔ができあがるのです。
その枠組みができあがれば、脳は英語化され、英語の語順のまま意味をつかむことが可能となります。
この枠組みのインストールが、次の2つの効果にもつながっていきます。
有意義な多読が可能になる
有意義な多読について、國弘さんは、ある高校生のエピソードをあげながら説明しています。
とある高校生が1年生の夏休みに『國弘流英語の話しかた』を読み、中学の教科書で音読をやってみた。
夏休み中ずっと音読を繰り返したこの生徒は、2学期になると別の中学から来た友達に異なる出版社の中学教科書を借りた。
ほかの友達にも声をかけた結果、合わせて4種類の教科書を手に入れることができた。
借りた4種類については、一晩で読むことができたのだという。
この生徒の歩みは、【①精読(意味理解)→②只管朗読(音読)→③多読(量をこなす)】という流れを表しています。
多読の効果を得るには、いきなり大量の英文を読むのではなく、しっかり精読して意味を理解したものを繰り返し音読して、英語の枠組みを脳に刻むことが大切。
これを省けば、多読はただ声に出すだけの作業になり、意味のある学びにはならないと國弘さんは指摘します。
つまり、多読はインストール済みの OS をアップデートする行為。だから、その元となる OS のインストールを音読で済ませておくことが必要なのです。
難しい英語に取り組む力がつく
難しい英文に立ち向かう力をつけるには、土台が必要です。國弘さんはこれを、数学の掛け算の九九にたとえます。
九九を暗記しておくことが、複雑な計算に対応するベースとなるように、音読を通じて「英語理解の枠組み」を徹底的に磨き上げておけば、どんな難解な英文でも恐れず向き合える力が備わるのです。
ぼく自身も受験期に、この効果を身をもって感じました。
浪人生活を始めた1学期から音読に取り組みはじめ、2学期には難関大学の上級講座の長文問題を見ても、難しいとは感じず、むしろ迎え撃つための準備ができていると実感しました。
それは、音読によって「英語の核」を築いていたからこそだと確信しています。
音読の取り組み方・注意点
次に、音読に取り組むうえでの大切なポイントと注意点をお伝えします。
- 意識を向けるべきは発音ではない
- 時間をかけるべきは意味理解ではない
- 繰り返すことの分量について
意識を向けるべきは発音ではない
音読に取り組むときにありがちなのが、発音にこだわる人。けれど、只管朗読の本質は「発音を磨くこと」ではありません。その目的はあくまで「英語のパターンを身体に染み込ませること」にあります。
音声の点に限れば、一生懸命に練習し、かなりのレベルまで仕上げる人はそれなりにおります。高校生のスピーチコンテストを聞いてもわかるでしょう。しかし只管朗読は、音の点で外国人並みになることを目指すものではありません。
引用元:國弘流英語の話しかた
もちろん、単語一つひとつの発音は大切です。ですから、単語学習の方で、それぞれの単語の発音を押さえておくべきです。
國弘さんも、「最初から文章単位で完璧に発音しようとするのは難しい」と言っています。だからこそ、まずは基礎の単語の発音を押さえ、それを積み重ねることが望ましいのです。
ギターの練習に例えるなら、まずコード一つ一つを正確に押さえることが基礎。細かなテクニックは後からついてきますよね。
音読も同じです。ただ「声を出して読む」こと、その単純な行為を愚直に続けることが、英語の核を作るのです。
②時間をかけるべきは意味理解ではない
意味理解はもちろん欠かせません。しかし、基礎を築く段階で、意味理解に時間をかけ過ぎては本末転倒です。
基礎力を作る段階では、一通りの意味を理解するのに、あまり時間を使ってはいけません。時間は理解したものを身につけるために使うのです。その比率は、一対九といっても決して誇張ではありません。
引用元:國弘流英語の話しかた
只管朗読が見つめるのは、意味理解のその先。
つまり、意味理解の方ではなく、OS をインストールするための音読に時間を費やすべきなのです。
國弘さんは、ハインリヒ・シュリーマンという考古学者の例を引き合いに出しています。
彼は「内容がわかっている本」を教材に選び、意味理解に時間を使うことを極力避け、何度も繰り返し朗読して、内容を身体に染み込ませることに集中したと言います。
意味の把握は「前提条件」。
本丸はそこから先の、音読による「枠組みのインストール」なのです。
繰り返すことの具体的な分量
ここまで来て、最も気になるのは「どれだけ繰り返せばよいか?」という点でしょう。國弘さんは「暗記してしまうほど読み込んだ」と表現していますが、具体的な数字は明示していません。
ぼく自身の経験では、1つの英文素材を、1日5~10回、1週間続ける。これを3ヶ月続けることが、最低限のラインだと感じています。
もちろん、これより多くても問題ありません。時間が許せば、1日30回読んでもよいでしょう。
この繰り返しこそが、英語理解の枠組みを確固たるものにしてくれます。
一方で、この分量を下回ると、なかなか効果が実感できないことが多いのも事実です。
音読は短距離走ではなく、長距離の旅路。
じっくり、着実に、コツコツと続けることが肝要なのです。
まとめ:「朗読」ではなく「只管朗読」であることの意味

國弘正雄さんの本を手にとり、「只管朗読」というワードに出会ったとき、胸の奥でふわっと感じていたものが、言葉として明確な形になったように思いました。
ずっと「こうやって英語を学ぶのが、自分には合っている気がする」と感じていた。だけど、それが正しいのかどうか、自信が持てなかった。そんな迷いに、静かに光を当ててくれたような出会いでした。
いまの時代、英語学習には効率やスピード、成果が求められがちです。けれど、自分がやってきたのは、毎日こつこつと、声に出して読み続けるという、どこまでも地味で、派手さのないやり方でした。
でも、その積み重ねにこそ、力がある。遠回りに見えても、まっすぐで正直な方法だったんだと、國弘さんの言葉が教えてくれたのです。
これからも、世間の学習情報に振りまわされるのではなく、自分のやり方を信じて、愚直に学ぶことに、もっと真剣に、もっと誠実に向き合っていきたい。
そんな気持ちが、静かに、でもはっきりと心に根を下ろしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
👉 『國弘流英語の話しかた』では、「只管朗読」のその先についても語られています。
📬 ことばが、どこかであなたに触れたなら──
小さな便りをお寄せいただけたら、とても励みになります。