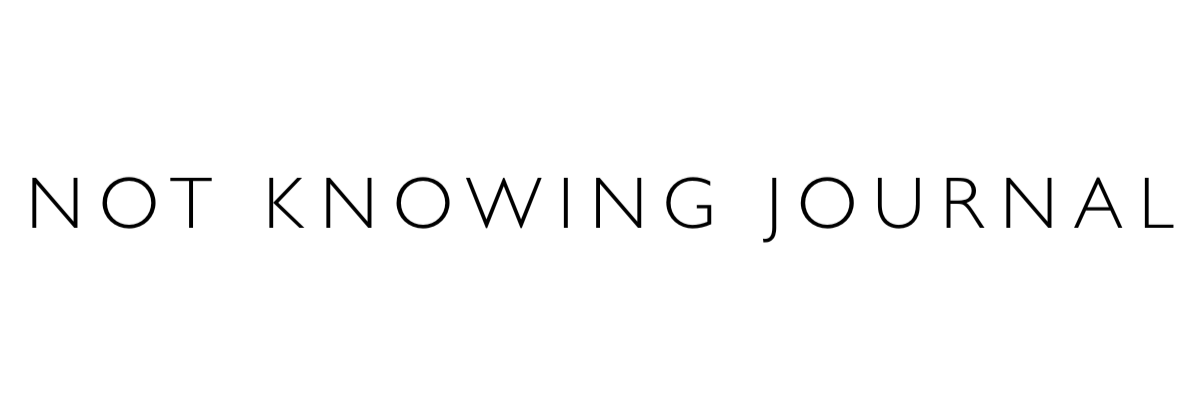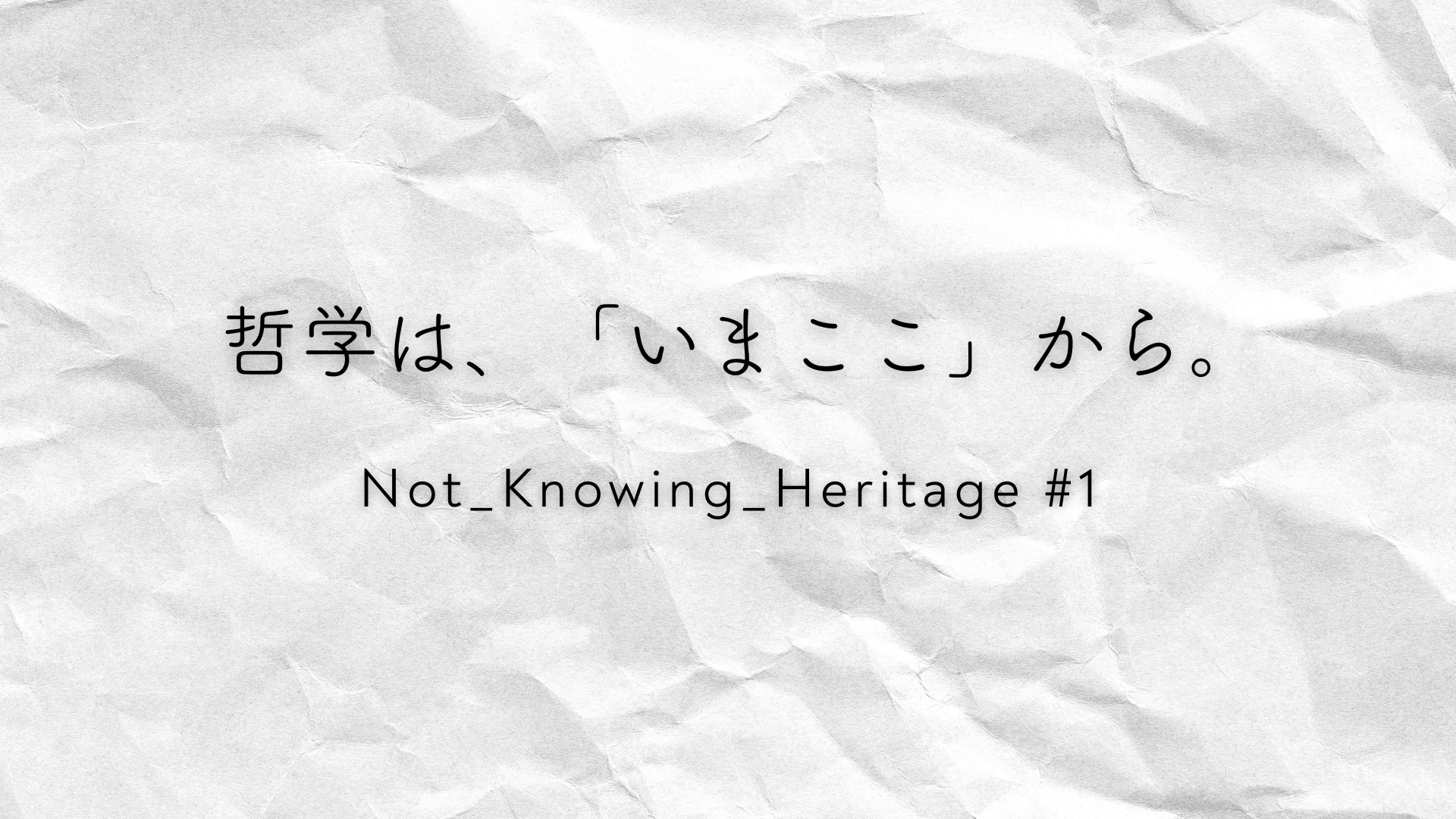哲学を学びたい。だけど、どこから手をつければいいのかわからない──。
いざ哲学を学ぼうとしたとき、ぼくはこんな悩みを持っていました。
本屋に並ぶ難解な書名。古代ギリシアから始まる長い歴史。時代も文脈も遠すぎて、「自分には無理かもしれない」と感じてしまう。
けれど、哲学とは、決して高尚な知識の体系ではありません。
むしろ、ぼくたちが日々の暮らしのなかで抱える、「なぜ?」や「これでいいのだろうか?」という問いの延長線上にあるものです。
だからこそ、“いま” という時代の思索から哲学を学びはじめる ことが、ごく自然なことだと思うのです。
本記事では、「現代思想から哲学に入る」という視点から、社会人にこそおすすめしたい学び方を提案します。
古典から始めなくてもいい。むしろ逆から学ぶことで、哲学はもっと身近で、自分の言葉で語れるものになる。
そんな新しい学びのかたちを、あなたと一緒に探っていけたら嬉しいです。
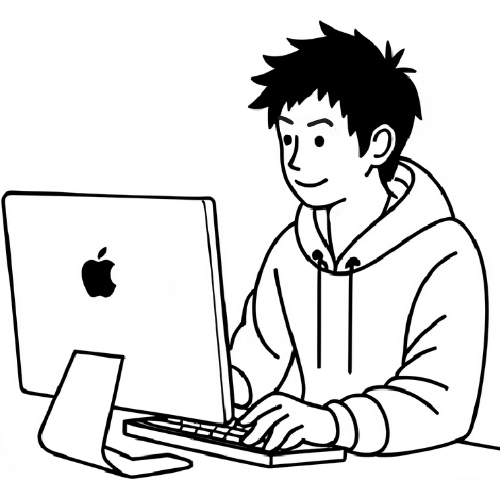
この記事を書いた人
ヒラク
NOT KNOWING JOURNAL 運営・執筆
早稲田大学 政治経済学部 政治学科
→ 総合医療機器メーカー
→ フリーランス
なぜ古典哲学は、私たちにとって遠いのか
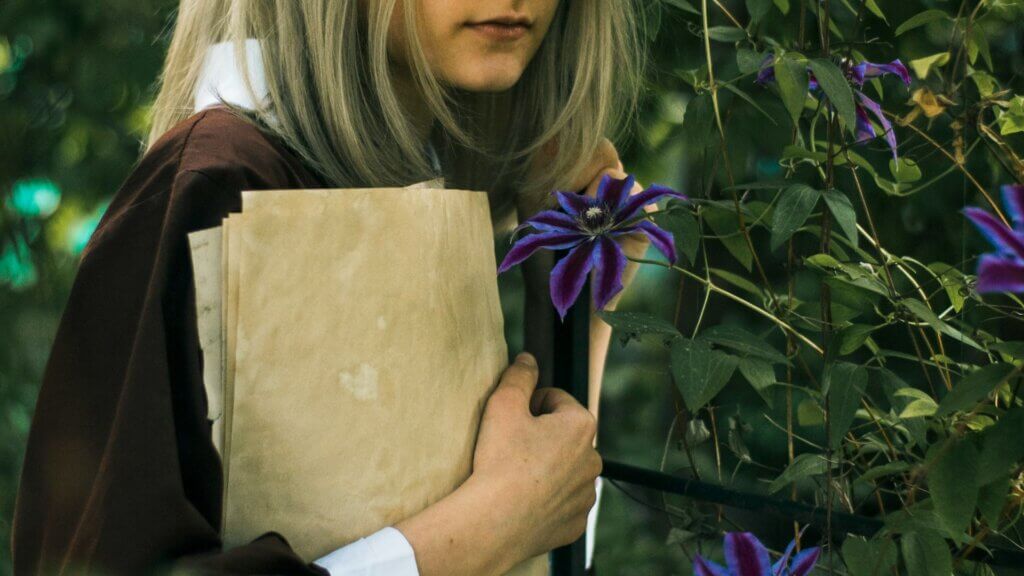
言葉が難しく、時代背景が遠すぎるという壁
哲学書を手に取ったとき、最初にぶつかるのは「言葉の壁」ではないでしょうか。
たとえば、プラトンやアリストテレス、カントやヘーゲルといった古典的な哲学者たちの文章には、抽象的で、日常とはかけ離れた語彙 がたくさん登場します。
さらに、それらの思想が生まれた背景──たとえばポリス社会、啓蒙時代、宗教改革など──も、現代に生きるぼくたちには馴染みの薄いものです。
言葉の難解さ と、時代との距離——
この二重の遠さが、哲学を「どこか別世界の知識」にしてしまっているのかもしれません。
もちろん、これらの古典には普遍的な価値があります。
けれど最初からそこに飛び込もうとすると、読むこと自体が目的になり、思考が置き去りになる──そんな矛盾が生まれてしまうのです。
「正統」から入ることが、かえって思考を止めてしまう
「まずは古代ギリシアから学ぶべきだ」
「カントやデカルトを理解していないと、哲学を語ってはいけない」
そんな “正統なルート” にこだわる声を耳にすることがあります。
たしかに学問としての体系を考えれば、その順番は理にかなっているのかもしれません。
けれど、ぼくたちが哲学に惹かれる瞬間は、もっと個人的で、もっと切実な問い から始まっているのではないでしょうか。
たとえば、「なぜ働くのか」「生きる意味って何だろう」「この社会は、どこかおかしくないか」といった、小さな違和感や、立ち止まりたくなるような感覚です。
それらを無視して、“順番” や “正しさ” を優先してしまうと、本当に考えたかったことが、かえって遠のいてしまう。
知らないうちに、哲学の世界に「思考停止」を持ち込んでしまうのです。
だからこそ、必ずしも「古典から始める」ことにこだわる必要はない のだと、ぼくは思います。
むしろ、自分の問いに即した入口から入るほうが、ずっと自然で、ずっと深く考えられるのではないでしょうか。
現代思想から哲学を学ぶという選択

「いま」に立ち上がる問いから始める
哲学に興味を持つ瞬間は、いつも突然です。
たとえば、何気ない日常でふと感じる違和感——「なぜ自分は、空気を読みすぎて疲れてしまうのか?」、「どうして、毎日の仕事がこんなにも空虚に感じられるのか?」。
そんな些細な問いが、実は深い思索の入り口であることに、ぼくたちはなかなか気づきません。
哲学は、決して「偉人の難しい言葉を読む学問」ではなく、「自分のなかから立ち上がる問いに、じっと向き合うこと」から始まります。
そして、現代思想はまさに、そうした「いま・ここ」にある問い に共鳴する学問です。
ハンナ・アーレントは、「なぜ人は考えないまま、世の中の空気に流されてしまうのか」を問いました。
ミシェル・フーコーは権力と知の関係から、世間の「当たり前」を追求しました。
こうした問いは、私たちの生活にもそっくりそのまま通じています。
つまり、現代思想から哲学を学ぶということは、遠くの知識に触れることではなく、自分自身に起きていることを深く知ろうとする行為 なのです。
思想は “いま” を理解するための道具になる
現代を生きるぼくたちは、言葉にしにくい不安や息苦しさと隣り合わせです。
SNS の洪水、意味を見出せない働き方、世界的な分断と暴力……。こうした状況の中で、「なぜこんなにも生きにくいのか?」という感覚を持つのは、ごく自然なことです。
けれど、その不安や疑問は、誰かにうまく説明することもできず、やがて「自分が弱いせいだ」と内面化されてしまうこともあります。
そこで、思想という道具 が力を発揮します。
哲学者たちは、必ずしも「正しい答え」を教えてくれるわけではありません。
けれど、彼らが編み出した言葉や概念は、自分自身の感情や違和感に「形」を与え、理解する手がかり になります。
たとえば、近年、資本主義や民主主義のあり方を問い直す思想家が多く登場していますが、それらに触れることで、「自分が感じていた閉塞感は、社会構造に由来するものだったのかもしれない」と気づくことがあるでしょう。
つまり、思想とはただの知識ではなく、世界と自分をつなぎ直すための、実践的な道具 なのです。
「いま」を生きるために哲学を学ぶ—— その入り口に、現代思想というジャンルは、じつにふさわしいものだと言えるでしょう。
“現代思想スタート” で哲学を学ぶ3つのメリット

哲学が「自分ごと」になることで、挫折しにくい
哲学の挫折の多くは、「読んでも意味がわからない」「生活と結びつかない」といった距離感から生まれます。ですが、現代思想から始めることで、哲学はぐっと「自分の問題」として立ち上がってきます。
たとえば、ジル・ドゥルーズは「人は思考を “強いられる” ときにしか、本当に考え始めない」と語ります。これは、何かにぶつかり、違和感を覚えたとき——仕事での息苦しさ、人間関係の葛藤、あるいは世界に対する説明のつかなさ——そんな “わたし” の実感から出発する哲学の姿です。
読書が “自分の中の問い” に根ざすことで、知識の暗記ではなく「生き方の探究」になります。だからこそ、続けることができるのです。

ジル・ドゥルーズ(1925–1995)とは?
20世紀フランスを代表する哲学者のひとり。
「差異」「リゾーム」「欲望機械」といった斬新な概念を生み出した思想家。
思想の根底には「固定されたものを壊し、新しい可能性を開く」という、強い自由への希求が流れている。
「既成の答えに満足できない」「枠を超えて考えてみたい」と思う方に、ぜひ触れてほしい哲学者。
読む順番に縛られない、自由な学び方ができる
哲学を学ぶ際、「どこから手をつければよいのか」と悩む人は少なくありません。しかし現代思想からのアプローチは、必ずしもカノン(正統的な順番)に従う必要がないという柔軟さを持っています。
ひとりの思想家から入ったとしても、その思想家のどこに着目するか(自らの内面についてなのか、他者との関係性についてなのかなど)によって、その後に読むべき本も枝分かれしていきます。
“問い” を手がかりに本を選ぶことで、読書のルートは人それぞれ異なってよいのだと気づきます。読む順番ではなく、「なぜそれを読みたいと思ったのか」という動機に忠実であること。そこから、自分だけの哲学の旅路が始まるのです。
現代の問題意識が、古典への橋渡しになる
現代思想は、いま私たちが生きる社会に直結した問題を扱っています。そこから読み始めることで、いわば “地続きの関心” として、過去の古典に自然と手を伸ばすことができます。
シモーヌ・ヴェイユの「不幸(malheur)」という概念は、現代の労働や疎外、無力感の問題と深くつながっています。そしてそこからさらに、プラトンの「魂の秩序」や、キリスト教神学といったあたりまで問いが伸びていくのです。
つまり、現代思想は「古典へ向かうための地図」のようなもの。いきなり古代ギリシアから始めるのではなく、まず現在地を知ることで、古典も “遠い誰かの思想” ではなく、“自分の続き” として読めるようになります。
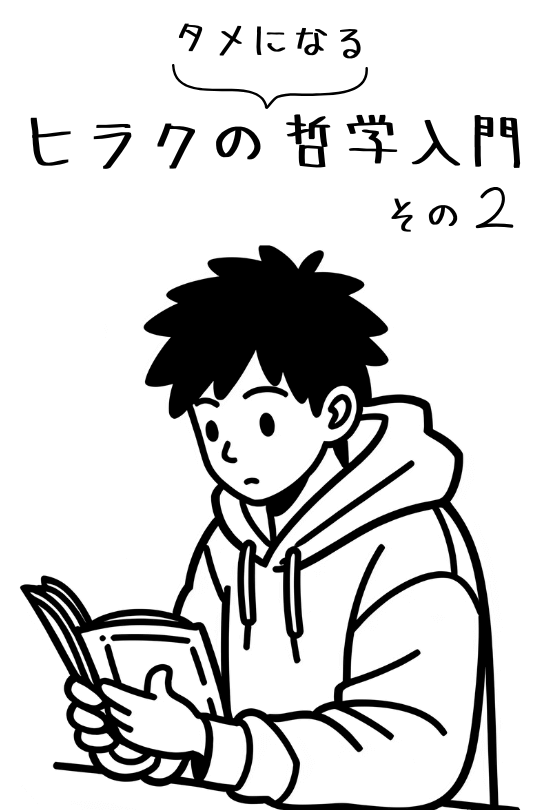
シモーヌ・ヴェイユ(1909–1943)とは?
フランスの哲学者・宗教思想家・社会活動家。
若くして命を終えながらも、深い思想と魂の叫びを遺した “20世紀の良心” とも言える存在。
単なる思索者にとどまらず、飢える人々と共に飢え、苦しむ人々の側に立つことを徹底した、まさに〈生きる哲学〉を実践した人物。
彼女の文章は、ときに苦く、ときに息が詰まるほどの切実さを帯びている。
社会人向け【哲学書 “逆行” ルート】の提案

ミシェル・フーコーから「社会を問い直す視点」を学ぶ
社会の制度や規範は、私たちの思考やふるまいにどれほど深く入り込んでいるのでしょうか。そして、そうした構造の中で、どうすれば「呑み込まれずに」生きていけるのでしょうか。
こうした問いに強く応答するのが、フーコーの思想です。
とりわけ代表作『監獄の誕生』では、「監獄」という制度を通じて、社会がいかにして「身体を従わせる技術=規律訓練」を発展させてきたかが、驚くほど鋭く描かれています。哲学や思想に不慣れな人でも、現代社会のしくみへの違和感から思考を始められるという意味で、この一冊から入るルートは非常に実践的です。
ぼく自身、これまで哲学の本を読んできたうえで、以下のようなルートをたどるのが良いのではないかと考えています。それぞれ、適宜入門書を活用し、無理のないかたちで読み進めることをおすすめします。
📘 読書ルート例|ミシェル・フーコーから古典へ
- フーコー『監獄の誕生』
‐ 社会が人を管理する仕組みを問い直す。
‐ 規律訓練、権力、知の関係に注目。 - ニーチェ『道徳の系譜』
‐ 「善悪」や「道徳」とは何かを解体的に考察。
‐ 権力への意志、ルサンチマン(怨恨)の視点から思考。 - カント『実践理性批判』
‐ 道徳や自由の根拠を、理性によって基礎づけようとする試み。
‐ フーコーやニーチェの思考の出発点として重要。 - ヘーゲル『精神現象学』(または『法の哲学』)
‐ 「歴史」と「社会の成り立ち」を弁証法的に捉える視点。
‐ 社会と個人の関係を動的に理解するための鍵。
✅ フーコーの入門書としては、以下の1冊がとてもわかりやすく、おすすめです。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
ハンナ・アーレントから「人間の在り方」を考える
現代思想において「人間とは、何か?」という根本的な問いに対し、強い光を当てたのが、政治哲学者ハンナ・アーレントです。
彼女の代表作『人間の条件』では、「労働」「仕事」「活動」という三つの行為のあり方から、人間の自由と公共性を再定義しました。
アーレントの思想は、政治や歴史に関心がある方はもちろん、「自分は社会のなかで、どう生きていくのか」を考えたい方にとって、強く響くはずです。
そんなアーレントを入口とした読書ルートは、例えば次のようになります。
📘 読書ルート例|ハンナ・アーレントから古典へ
- アーレント『人間の条件』
‐ 人間の活動と公共性の本質を問う、アーレントの主著。
‐ 「行動すること(アクション)」が、いかに他者との関係を生み出すのか。 - ハイデッガー『存在と時間』
‐ アーレントが学んだ師、存在論的視座から「世界内存在」としての人間を描く。
‐ 「現存在(ダス・ザイン)」という概念を通して、個人の自由や責任の根源に迫る。 - カント『判断力批判』
‐ アーレントが政治的判断や「共通感覚(センス・コムーニス)」の概念において参照した。
‐ 審美的判断と倫理的判断の接続を通して、公共的な理性の働きについて深く学べる。 - 古代ギリシア哲学(プラトン『国家』、アリストテレス『政治学』)
‐ アーレントが強く影響を受けた古典的思想。
‐ 「ポリス」「市民」「公共性」などの政治的概念の源流を探ることができる。
✅ アーレントの入門書としては、以下の書籍がおすすめです。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
まとめ — 哲学は「逆から」でも、深く学べる

「哲学」と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは、難解な言葉、厚い本、古い時代。そんなイメージの前に立ちすくみ、「自分には無理だ」と感じてしまう人も少なくないでしょう。けれど、ぼくたちはもっと自由に、もっと柔らかく、哲学に出会ってもよいのです。
むしろ、「いま、この社会で、何が生きづらさの原因なのか」「なぜ自分はこんなにも違和感を抱えているのか」といった、身のまわりの素朴な問いから出発すること こそが、哲学の本質にふれる道ではないでしょうか。
現代思想は、そんな「いま」の感覚に、ことばを与えてくれる営み です。そして、そこから一歩ずつ、問いを抱いたまま過去へとさかのぼっていけば、やがて古典哲学が語ってきた深淵な思索とも、静かに響き合うことができる ようになります。
哲学に、決められた順番はありません。
「わからない」という感覚を起点にしていい のです。
「わかろうとしつづける」ことこそが、考えるという行為なのですから。
あなたの中の「なぜ?」を大切にしながら、少しずつ、哲学の本を開いてみてください。
その歩みはきっと、いままで見えなかった世界の輪郭を、そしてあなた自身の輪郭を、静かに照らしてくれるはずです。
📬 ことばが、どこかであなたに触れたなら──
小さな便りをお寄せいただけたら、とても励みになります。