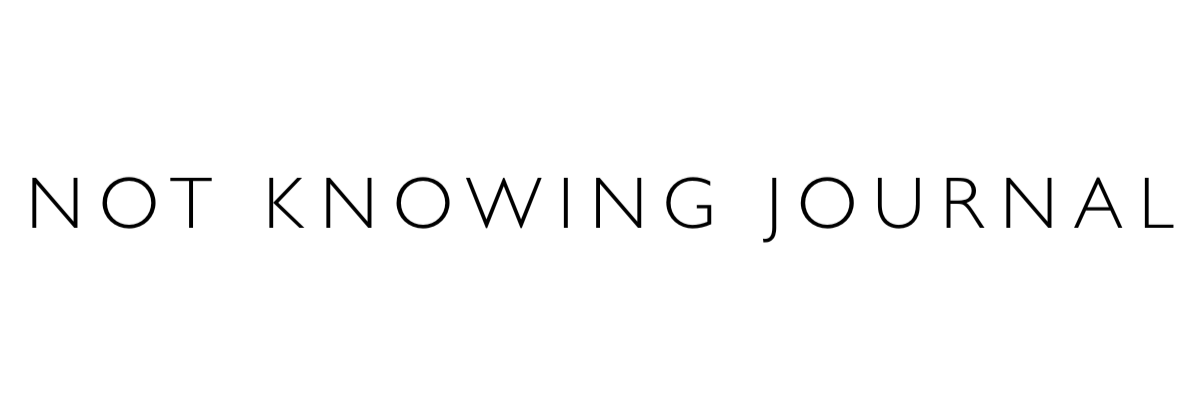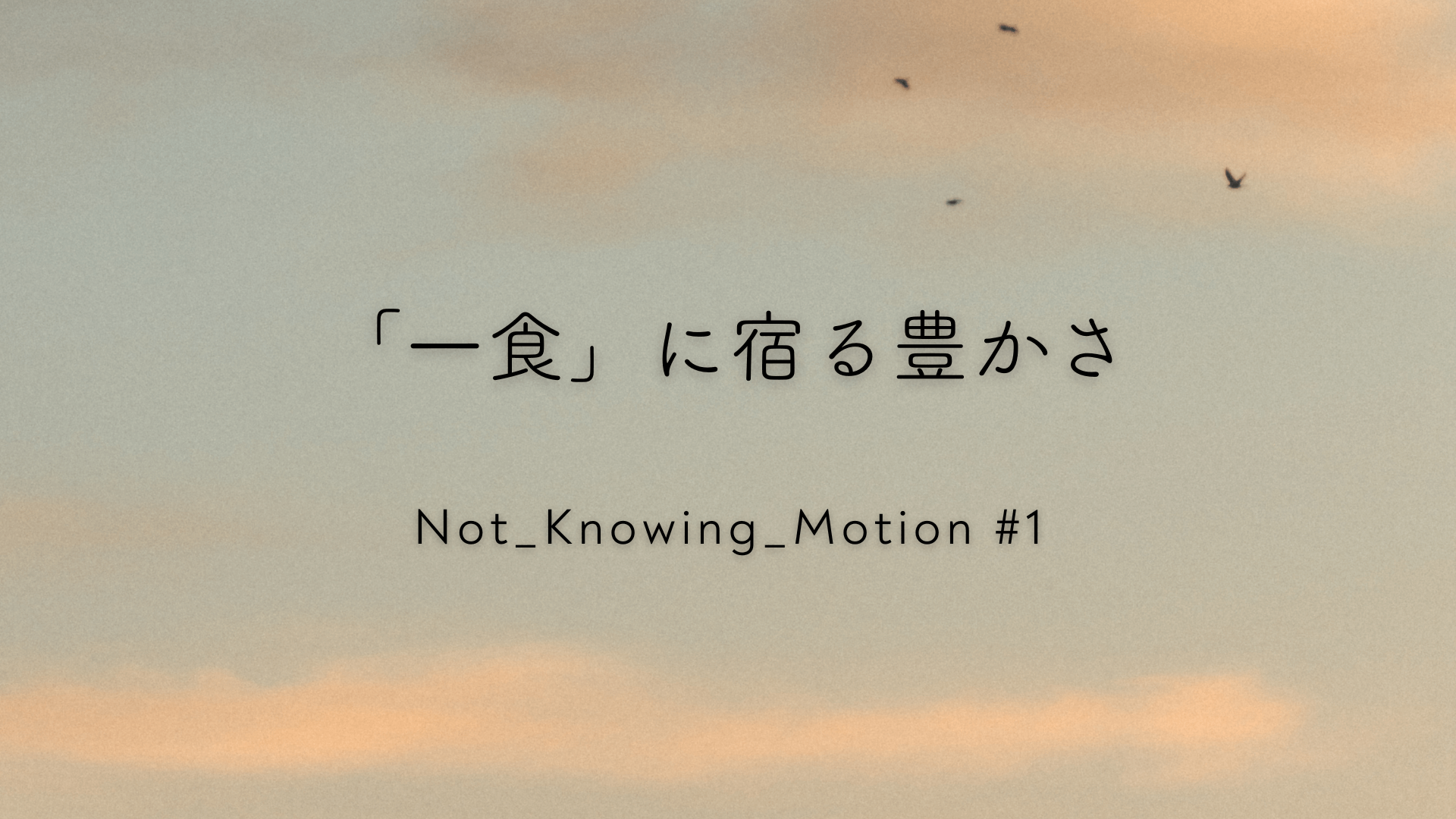朝、昼と食事を抜く生活は、はじめは「ちょっとした実験」くらいの気持ちで始めた。
けれど、やってみると意外にも面白く、そして少し不思議な時間が流れる。
お腹が鳴る午後、仕事や家事をしていると、感覚がいつもより研ぎ澄まされる瞬間がある。
香りや音が鮮やかに届き、頭が妙にクリアになる——そんな時は、「空腹って、悪くないかも」と思えてくる。
もちろん、空腹の波はゆるやかなばかりではない。
急に甘いものが恋しくなったり、夕方になると時計ばかり気にしてしまったり。
けれど、その先に待つ一食の時間は、普段よりずっと豊かに感じられる。
箸を手に取る喜び、噛みしめる一口目の美味しさ——それは、一日を締めくくる小さなご褒美だ。
ここでは、一日一食を続けながら見えてきた、体の変化や心の揺れ、そしてちょっとした発見をお話ししたい。
小さな習慣の変化が、日常をどう塗り替えていったのか——その記録を、これから綴っていく。
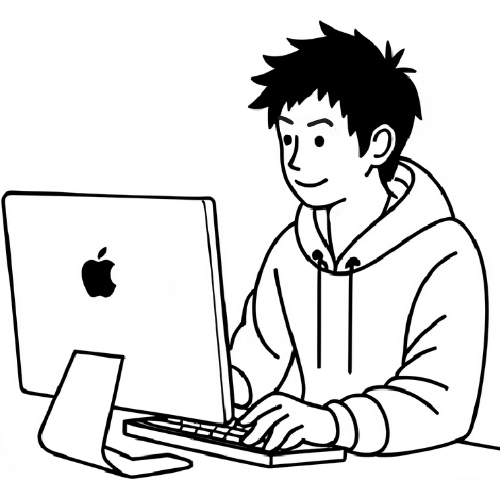
この記事を書いた人
ヒラク
NOT KNOWING JOURNAL 運営・執筆
早稲田大学 政治経済学部 政治学科
→ 総合医療機器メーカー
→ フリーランス
はじめに — 3年続けて見えてきた景色

きっかけは小さな好奇心
一日一食という暮らしは、じつは初めてではない。
大学時代、学費や生活費に追われていた頃、やむを得ずそうしていた時期があった。お金のために選んだはずのその日々はしかし、意外にも快適だった。空腹にはつらい側面もあったけれど、体も頭も冴える。あの感覚は、どこか不思議で、少し誇らしくもあった。
社会人になると、二食、三食の生活に戻った。理由は簡単で、周りに合わせるためだ。昼休みに食事の誘いを断るのは気まずいし、みんなが弁当を広げるなか、自分だけ座っているのも妙に居心地が悪い。空腹よりも、同調圧力のほうが重く感じられた。
そして3年前、フリーランスになった。時間も行動も、自分の裁量で決められるようになったとき、あの大学時代の感覚が自然と思い出された。再び一日一食へ——それは仰々しい決意ではなく、静かに元の場所へ帰るような意識、そしてあの時の感覚をもう一度味わってみたいという、ちょっとした好奇心でもあった。
習慣になってからの、静かな変化
最初の数週間は、食事の回数が減ることに少し戸惑いもあった。けれど、一日、また一日と重ねるうちに、それは当たり前の生活の形になった。
一日一食は、想像よりも “特別” ではない。空腹に慣れると、むしろ三食食べる生活の方が何か異質なものに思える。
それは食事以外のことについてもそうだ。世の中で「普通」とされるものに対して、自分自身の感覚で向き合えるようになる。
食べることを減らすだけで、こんなにも心の景色が変わるのかと、自分でも少し驚いた。食べることに対する考えというだけではなく、生きることに対する考えが根本から変わるような、そんな感じがした。
「食べない時間」がくれた自由 — 時間の余白

食事に費やす時間が消えた日々の風景
朝食や昼食の準備、食べる時間、そして片づけ——そのすべてが、消えた。ほんの一時間か二時間の話なのに、無くしてみると、その広がりは意外なほど大きい。
朝はコーヒーを一杯だけ淹れ、静かなまま仕事に入る。昼には食事のために机を離れることもなく、集中が途切れない。外に出かける日も、「どこで昼を食べようか」と考える必要がない。食事のための段取りが一つ減るだけで、日常の景色はこんなにも軽くなるのかと、何度も思った。
そして、その空いた時間は、ただの余り時間ではなかった。読書をしたり、散歩に出たり、あるいは何もせず窓の外の雲を眺めるだけでもいい。食事のために割り当てていた “予定” が消えると、その場所に “選べる自由” が入り込む。日々の中に、静かで柔らかな空間が生まれた。
時間に追われなくなったことがもたらす小さな解放
時間に縛られない暮らしは、思っていた以上に心を静かにする。朝、昼の食事が無くなったことで、時計の針を気にする回数が減った。朝の仕事前に急いで何か一口食べなきゃとか、昼までに仕事を片付けなければとか、——そうした小さな焦りが、いつの間にか消えていた。
「時間が足りない」と感じていたのは、もしかすると実際に忙しかったのではなく、時間を “区切り” で消費していたからなのかもしれない。今は、ひとつながりで流れる時間を、そのままゆったりとたどる感覚がある。食べないことで得たのは、ただの空腹ではなく、心の奥に広がる、澄んだ余白だった。
そして、その余白は確実に生活の質を変えていった。自分のペースで物事を進められることは、単なる効率の問題ではなく、生き方そのものに関わっている。時間にコントロールされるのではなく、時間をコントロールしているという感覚。忙しいことを良しとする雰囲気のあった会社員時代には、出会うことのなかった感覚だ。
消費との距離感が変わる — お金と選択

外食や配達、行列に抱いた違和感
一日一食の暮らしに慣れていくと、いつのまにか「外食」という行為が少しずつ色あせて見えてきた。同僚と昼休みを使って美味しいラーメン屋を捜し歩き、休日には街の新しい店を巡ることが生活の彩りだった。クチコミで評判の店があれば、行列に並ぶことだって厭わなかった。けれど、空腹を通して日々を過ごす中で、その景色がまるで違う顔を見せ始めたのだ。
「本当に、こんなに時間をかけてまで食べる必要があるのか?」
「流行に流されて、貴重な時間を浪費しているのではないか?」
心の奥から、そんな疑問が静かに、しかし確かに湧き上がった。長い列の先にあるものは一体なんだろう——と。
そして、フードデリバリーも違った角度から見るようになる。色鮮やかに並ぶ料理の写真たち。その背後には、使い捨ての包装、一皿の料理を運ぶためだけに吐き出される排気ガス、そして瞬間の満足感を求める消費の連鎖が見え隠れする。便利さに身を任せていた自分が、いつしか消費社会の流れの中に巻き込まれていたのだと気づかされる日々だった。
無駄な消費の見直しと、新しい選択基準
一日の食事が一度になると、「質素に暮らす」という生き方の中に、自然と美しさを感じるようになってくる。「少し」のなかに、以前は想像もつかなかった「豊かさ」が詰まっているのを発見する。こうして、食だけでなく、日常の消費活動全般が静かに変化していく。
服や雑貨にはじまり、情報や時間の使い方まで、「本当に必要か」と問うては答えを探す。流行に踊らされることはなくなり、むしろ「本当に価値のあるもの」だけが残っていった。
その結果、部屋の中は不要なものが減り、心地よい空間へと変わった。財布の中身にもゆとりが生まれ、消費に対する不安や焦りから解放された。消費とは敵でも悪でもない。ただ、その距離を見極め、健やかな関係を築くことが大切なのだ。
一日一食は、ぼくにとってその距離感を繊細に調整するためのレンズとなった。忙しさや流行の波に飲まれそうな現代で、自分自身を見失わずにいられる、そんな確かな感覚を教えてくれたのだ。
食事の質と身体のささやかな変化

一食で深まる「味わう力」と加工食品への拒否反応
一日一食にしてから、食事の時間は以前よりもはるかに特別な意味を持つようになった。朝も昼も口にしないまま過ごすと、夕方には身体全体が「食べる準備」を整え、感覚が研ぎ澄まされていく。用意した食事の匂いが鮮烈に届き、湯気の温度や香りの層まで感じ取れるようになる。
野菜のおいしさ を感じられるようになったのも大きな変化だ。味覚が研ぎ澄まされたことで、野菜の中にあるささやかな甘みが、以前よりも鮮やかに感じられる。空腹が作る集中力が、野菜という素材を深く味わわせてくれるのだ。
この集中力は逆に、添加物まみれのもの や、過度に味付けされたもの を受け付けないようにした。たまにスナック菓子やファストフードを食べると必ずお腹を壊してしまう。これは、ぼくの体が弱くなったのではなく、正常に戻ったということだと思う。“人間らしい” 食生活をしていれば、“人間らしくない” ものを受け付けない体になるのだ。
一日に一度だけの食事ということもあり、一食当たりの量に制限を設けてはいない。ただ、「好きなだけ食べる」と決めても、実際には満腹以上を欲しなくなった。必要な分だけを自然に受け入れる。これは単に食事量の話ではなく、食べるという行為そのものに対する姿勢が変わった証拠でもある。一食をしっかりと味わうことが、結果として心の満足度を高めている。
見た目の若さ・運動と空腹の関係
一日一食生活を続けてから、「若く見える」と言われることが増えた。体重の変化は緩やかだが、顔まわりや腰回りが引き締まり、輪郭がはっきりしてきた。肌の色も明るくなり、吹き出物が減った。これらはおそらく、食事の質の向上や消化器官の休息時間が増えたこと、そして運動習慣の影響が組み合わさった結果である。
体の軽さは、日々の行動に直結する。朝のランニングは特にその効果を実感しやすく、空腹の時間が筋肉や関節の動きを軽やかにする。走り終えたあとの疲労感は少なく、むしろ集中力や気分の冴えが続く感覚がある。一方で、雨の日など走れない日が続くと、空腹感が強まりやすい。カロリーを消費していない日の方が、食べ物を欲するのだ。そのようなときは、昼に果物やナッツを少し加えて1.5食にする。
この柔軟さこそが、継続の鍵だと感じている。空腹は「我慢するもの」というより、「対話するもの」と捉えるようになった。無理に耐えるのではなく、体の声を聞きながら食べるタイミングや内容を調整する。そうすることで、見た目の変化だけでなく、日常全体の質が底上げされていく実感がある。
まとめ — ゆっくりと、時間と消費を取り戻す

3年間の一日一食生活は、決して「我慢」の物語ではなかった。むしろ、日々の暮らしに潜んでいた無数の「当たり前」を、静かに手放していく過程だったように思う。食事の回数を減らすことで、空腹の時間が増え、同時に時間の余白も広がった。その余白は、やがて考える時間、走る時間、ただ窓の外を眺める時間へと変わっていった。
消費の面でも、食にまつわる選択が大きく変わった。外食や衝動買いが減り、本当に必要なものだけを選ぶ眼が養われた。節約や倹約という言葉よりも、「選び取る喜び」という感覚に近い。時間とお金、その両方において、消費の主導権が少しずつ自分に戻ってきたのだ。
もちろん、この生活を誰にでも勧めたいわけではない。体質や環境、生活のリズムによって向き不向きはある。ただ一つ確かに言えるのは、食べることを「減らす」選択が、結果として自分の中に「増える」感覚をもたらしたということだ。自由な時間、集中力、そして小さな満足感。それらは以前よりも確かに豊かになった。
ゆっくりと、しかし確実に、時間と消費は自分の手に戻せる。そう気づいた今、ぼくはまた明日も、一日一食の静かなリズムを選び続けるだろう。
📬 ことばが、どこかであなたに触れたなら──
小さな便りをお寄せいただけたら、とても励みになります。