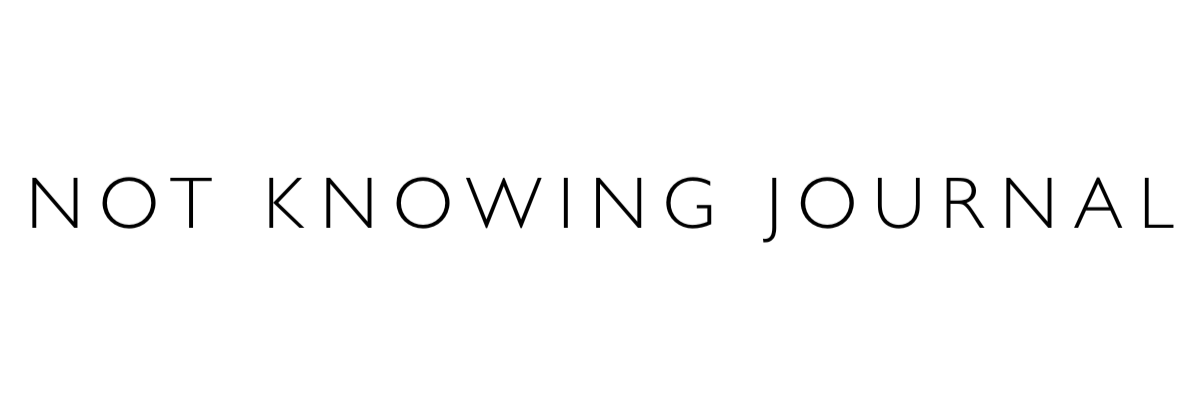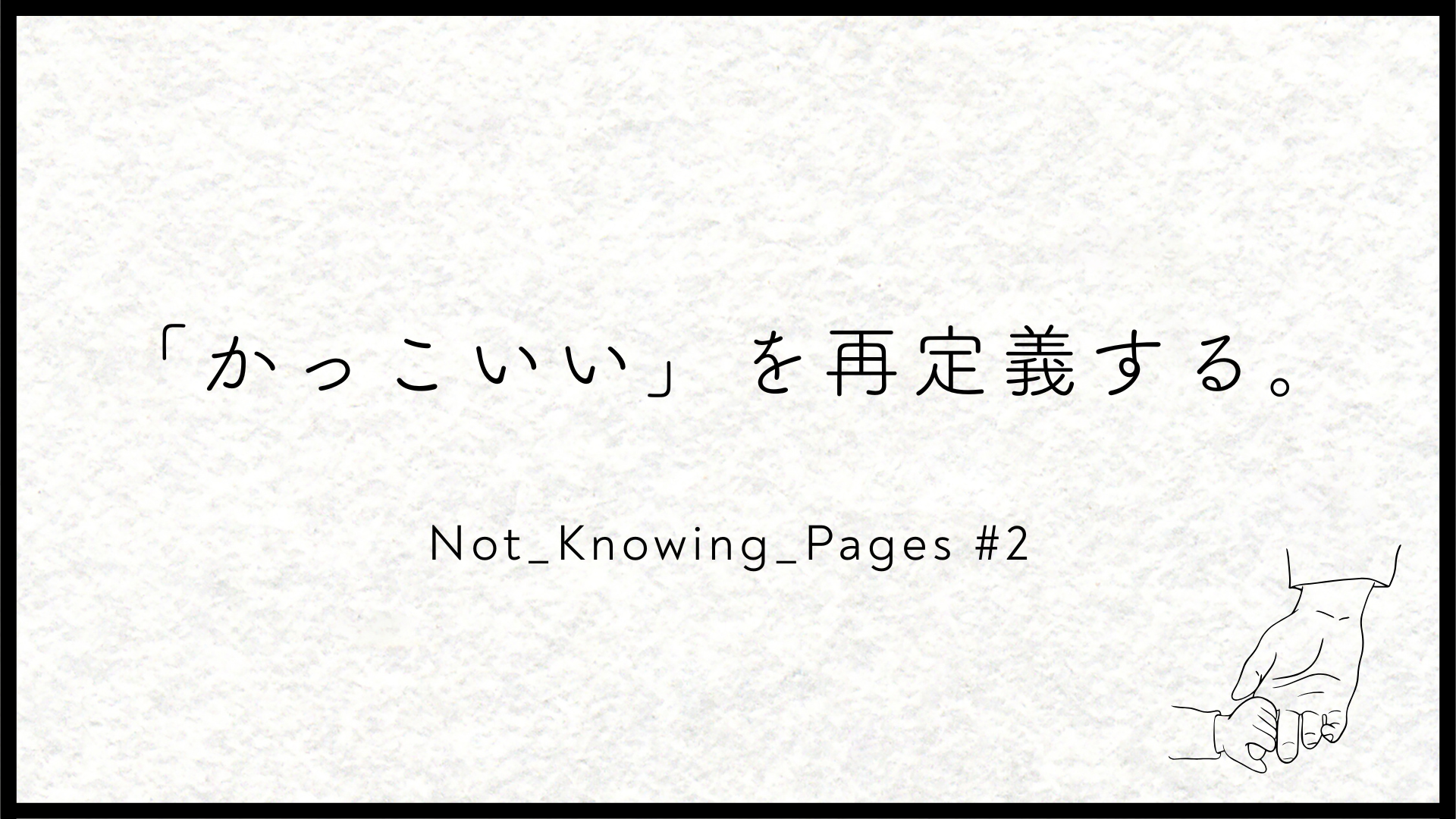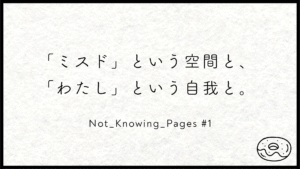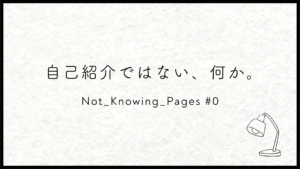かっこいい大人って、どんな人だろう?
社会的に成功していて、収入があって、見た目もスマートで…そんなイメージがあるかもしれない。
でも正直、それだけじゃないと感じることはないだろうか。
最近、ニュースを見ていて思う。
大人が責任を取らなかったり、自分を守ることばかり考えていたり──
そんな姿ばかり目にする今の子供たちは、かわいそうだ。大人のあるべき姿を知らぬまま、彼らは大人になっていく。
ぼくは、ちょっとだけ損しても、静かに正直に生きている人に、かっこよさを感じる。
誰に褒められなくても、光が当たらなくても、自分の中の「筋」を通して生きている。
そんな生き方って、ものすごく凛としていて、心からかっこいいと思う。
この文章は、そんな「報われないかもしれないけれど、誠実に生きるってやっぱりかっこいい」と思う気持ちから書いている。
大げさなことは言えないけれど、「ちょっとだけ損してみる」っていう選択肢も、実はとても魅力的なんじゃないか──
そんな視点で「かっこいい大人像」を模索してみたい。
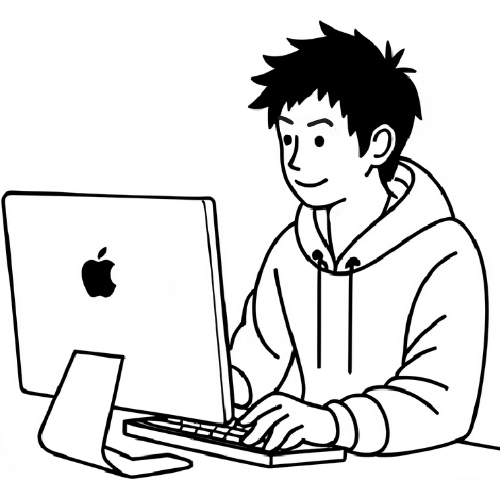
この記事を書いた人
ヒラク
NOT KNOWING JOURNAL 運営・執筆
早稲田大学 政治経済学部 政治学科
→ 総合医療機器メーカー
→ フリーランス(ライター・ブロガー etc)
欲望に溺れる大人たち──失われた「美しい大人像」

「辞めない総理」と「盗撮する教師」──崩れゆく倫理観
この国の総理は、就任以来、国政選挙で立て続けに敗れた。それなのに、いっさい責任を取ろうとしない。
かつての総理が選挙で惨敗したときに、責任追及の先頭に立っていたのが、ほかならぬ彼だった。
立場が逆になった今、彼はその座を手放そうとはしない。
思えばこれまでの政治家たちも、決して綺麗ではなかった。
密室談合、裏金、派閥争い──子どもにとっては遠い世界の、ミステリアスな “オトナの悪” だった。
だけど、今の総理は毛色が違う。
選挙結果という民意を否定したとか、民主主義の危機だ、などという高次元の話ではない。
「辞めたくない、辞めたくない」とただひたすらに駄々をこねている。コドモじゃないか。
教育現場に目を向ければ、教師が教え子を盗撮し、それをSNSで共有していたという。
表では「教育者」として立派な顔をしながら、裏では欲望に負け、卑劣な行為に手を染めている。
善人を演じ、人格者を装いながら、見えないところで腐敗している。
芸能界では、大物タレントが…。いや、もうやめよう。自分でも話していて暗澹たる気持ちになる。
三島由紀夫は、将来の日本を案じてこう言った。
「このまま行ったら日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜け目がない、或る経済大国が極東の一角に残るのであろう。」
もはや、日本は中間色を通り越して、真っ黒に汚れてしまっているのではないか。
長らく「いまどきの若者は…」という言葉が口癖のように使われてきた。
だが、ぼくたち大人は、もうその言葉を使うことはできない。
ぼくらの世代こそが、もっとも醜く、もっとも腐っている──
そんな疑いを、否定できなくなっている。
「かっこ悪い大人」があふれる国で、子どもは何を思うか?
今の子どもたちは、かわいそうだ。
彼らは「かっこいい大人」を知らない。
「かっこいい大人とは何か」を知らないまま、大人になっていく。
ぼくには甥っ子が二人いる。小学生と保育園児だ。
二人ともやんちゃで、かわいらしい。
だけど、子供というのは見た目に反して、ものすごく鋭敏だ。
かつてのぼくたちがそうであったように、彼らも大人の「背中」を見ている。
大人の生き方を見つめて、自分の価値観を形作っていく。
一国の総理が駄々をこねているこの国で、彼らはどのように成長していくのだろうか。
欲望に溺れて身を亡ぼす大人たちを見て、何を思うのだろう。
彼らは、「早く大人になりたい」と思うだろうか。
ぼくは彼らに、ぼく自身の生き方を通じて「かっこいい大人」の姿を見せたい。
かっこいい大人だって、ちゃんといるんだよ──と背中で示したい。
そうしなければ、この時代に生まれてきた彼らが、あまりにもかわいそうだ。
ぼくは、ものすごく弱い人間だ。だらしなくて、自分に甘い。
だけど、そんなぼくでも、自らの生き方を問い直さざるを得ないほどに、この国の「大人像」は崩壊してしまっている。
ほんの少しだけでいい。
自分が「かっこいい大人」として、子どもに何を伝えられるのか。
その問いかけこそが、未来を変える一歩になる。
本当にかっこいい大人とは──「報われたい」気持ちをそっと手放す

報われる生き方──大谷翔平・井上尚弥が象徴するもの
いまの時代、「かっこいい大人」としてよく名前が挙がるのは、大谷翔平や井上尚弥といったアスリートたちだ。
彼らの生き方は、確かにかっこいい。
夢を語り、努力を重ね、それを実現していく姿は、まさに現代におけるヒーローだ。
普段は礼儀正しく、偉そうな振る舞いは見せない。そして、試合ではきちんと結果を出す。
その背中には、確かに「大人としての品格」がある。
そして、ぼくらはどこかでこう思う。
「努力が報われるって、やっぱりいいな」と。
報われる人の生き方が、光を放つのは当然だ。
それは、子どもたちにとっても希望になるし、大人にとっても理想の投影となる。
だから彼らの生き方を尊敬し、見習うのはとても健全なことだと思う。
だけど、「報われる生き方」だけが、かっこいい生き方ではない。
──ぼくは、そう思うのだ。
報われない生き方──ちょっと損する、その静かな美学
大好きなあの人の幸せを思い、身を引く。
後輩のミスを、自分の責任として受け入れる。
強引に割り込んできた車を、先に行かせてあげる。
そんなふうに、「少しだけ損をする」生き方がある。
目立たない。評価もされない。SNS映えもしない。
でも、そういう生き方の中に、ぼくはひそやかな美しさを感じてしまう。
それはきっと、「報われたい」という気持ちを手放す勇気 だ。
誰かに認められなくてもいい。
損得ではなく、「どう在るか」で選ぶ。
ぼくは思う。
人が「美しい」と感じるものには、たいてい何か“損”が含まれている。
無駄に見える努力、報われない情熱、不器用な誠実さ。
そうしたものが、なぜか心を打つ。
だから、もし今日、何かひとつ選ぶとしたら──
「ちょっと損する」ほうを、選んでみるのもいいかもしれない。
それだけで、ほんの少し、大人としてかっこよくなれる気がする。
報われないことの中に、ぼくが見出す美しさ

「成功しない人生」に宿る静かな倫理
世の中には、「成功しない人生」がある。
誰もが大谷翔平になれるわけではない。
どれだけ頑張っても評価されず、努力が徒労に終わる。懸命に働いたあげく、出世街道から外れる。
けれど、だからといって、その人生が「失敗」だとは思わない。
むしろ、そのような生を、どう受け止めるか。どう意味づけるか。
そこにこそ、深い“倫理” が宿るとぼくは思う。
ぼくは、歴史上の人物の中で 乃木希典 をもっとも敬愛している。
彼は軍人として、ひとりの人間として、国家のために「大いなる損」を引き受けた人だった。
日露戦争後、ある学校で演説を頼まれた乃木は、壇上に上がることを拒み、その場で「諸君、私は諸君の兄弟を多く殺した乃木であります」と一言言うと、その後は言葉に詰まり、ただ涙にくれたという。
「名誉」よりも「栄華」よりも、「責任」に向き合った人だった。「得」と「損」が転がっていれば、迷わず「損」を選ぶ人だった。
その生き方に、ぼくは強烈に惹かれるのだ。
彼の生き方には、たしかな価値がある。
それは、現代のモノサシでは測ることのできない価値。数字では表せない美しさだ。
彼の生に宿る倫理は、時間を超えてぼくたちの心に問いを投げかける。
──「おまえはどう生きるのか」と。
この社会は「成功」というものにとらわれすぎている。
富、地位、人気、結果──
それが、人間の視野を狭くしている。生き方を窮屈にしている。
みんなが「損」を避け、「得」の方へなだれ込む世の中になってしまった。
それが「自分さえよければいい」という考えにつながり、あの総理や、あの教師や、あのタレントを生み出した。
「勝ち組」「負け組」という言葉が、日常的に使われている。このことの異常性を、もはや誰も指摘しない。
本当に尊い生き方というのは、むしろ “負けること” の中でこそ、磨かれていくのではないか。
声高に語られることはないかもしれない。
称賛も拍手も起きないかもしれない。
でも、その人が選んだ「不器用な誠実さ」は、沈黙のうちに、周囲の人間を育てていく。
子どもたちは間違いなく、その清らかな目で、その誠実さを見つめている。
「報われない」へ向かうということは、ぼくたちのあり方を根本から変えることだ。
誰にも評価されなくても、自分の信じる道を歩むことは苦しさを伴うだろう。
——だが、そこには美しさがある。
子どもたちは、“損の美しさ”を本能的にわかっている
子どもは、驚くほどよく見ている。
大人がどんな顔で話しているか、誰にどう接しているか、
言葉と行動が一致しているか──
大人が思っている以上に、細部を見つめている。
たとえば、職場で理不尽なことに耐えている親の背中を、
街中で腹が立つようなことがあってもグッとこらえる様子を──
子どもは記憶のどこかにそっとしまっている。
今の時代ほど、正義感が薄っぺらくなってしまった時代はないだろう。
SNS やコメント欄では、「“自称” 正義」が溢れている。
正義というものはささやかに行使するものだ。振りかざした瞬間に、醜くなる。
子どもたちはそんな薄っぺらい「正義感」よりも、浅はかな「自尊心」よりも、
もっと静かで、奥行きのある“姿勢” を見ているのだ。
ちいさな子どもは、まだ「損得」の論理を知らない。
けれど、「耐えること」「譲ること」「受け入れること」の中に、無意識に美徳を感じ取るはずだ。
美しく在るとは、どういうことか──
その感覚の土台は、他でもない、ぼくたち大人のふるまいによって形づくられる。
だからぼくは、彼らの前で、
「少しだけ損をしている大人」でありたいと思う。
“損を取る人”こそが、本当の意味で、強いのだと示したい。
かっこいい言葉で飾る必要はない。
うまく生きろと言いたいわけでもない。
ただ、誠実に、静かに、世の中の損を引き受けている大人がいる──
その記憶が、彼らの中に残ってくれたなら、
ぼくの人生も、少しだけ意味があると思える気がするのだ。
結び──「ちょっと損する」ことから、大人をはじめよう

報われない覚悟ではなく、報われなくてもいいという余裕
ぼくたちは、つい「報われるかどうか」に敏感になってしまう。
努力が結果に結びつくか。人に認められるか。意味があるかどうか。
その問いの前で、自分の選択や行動を測ってしまう。それが、生き方を狭めている。
「報われない覚悟」というと、どうしても重い。暗い。
だから、「報われなくてもいいという余裕」に置き換えるといいかもしれない。
覚悟は強さだ。でも、余裕は優しさだ。
余裕のある人は、他人の未熟さにも、世界の不条理にも、
怒らず、嘆かず、静かに受けとめることができる。
今の日本にだって、明るい材料はある。
自分の生命を削って、日本のために尽くす政治家もいる。
家族との時間を犠牲にして、生徒と向き合う教師だって少なくない。
彼らは、自分の「損」を誇ることなく、ただ淡々とそこに在る。
そんな人たちの生き方には、静かだけれど確かな美しさがある。
評価されなくても、成功しなくても、その人生そのものが子供たちへの贈り物になりうる。
かつて内村鑑三は「勇ましく高尚なる生涯」こそが、後世に遺すことのできる最大の遺産であると説いた。金でも事業でもなく「生き方」を遺せ、と説いた。
ぼくは、お金を遺せない。事業も残せない。
けれど「生き方」を遺すことはできるかもしれない。
子供たちに「誠実で、美しい生涯」を示してあげることはできるかもしれない。
そんな大人の背中こそが、未来に静かな希望を手渡していくのだと思う。
📬 ことばが、どこかであなたに触れたなら──
小さな便りをお寄せいただけたら、とても励みになります。