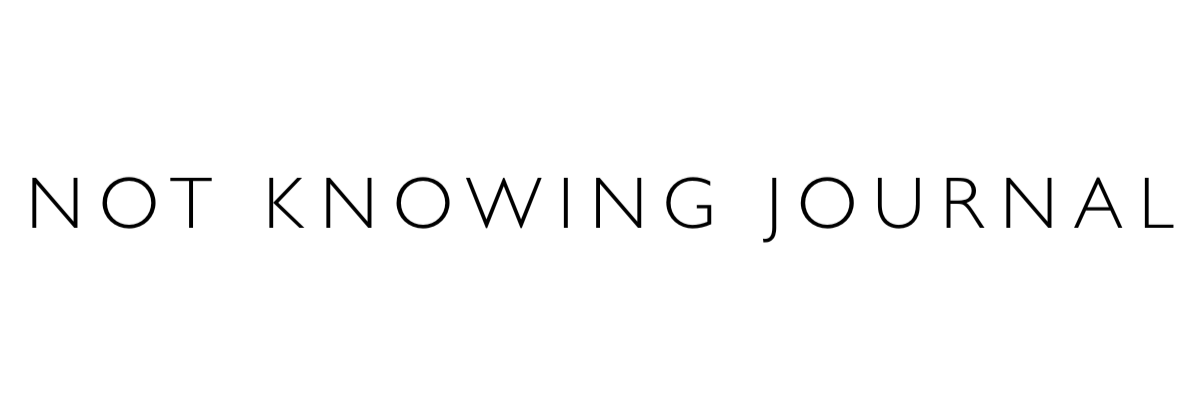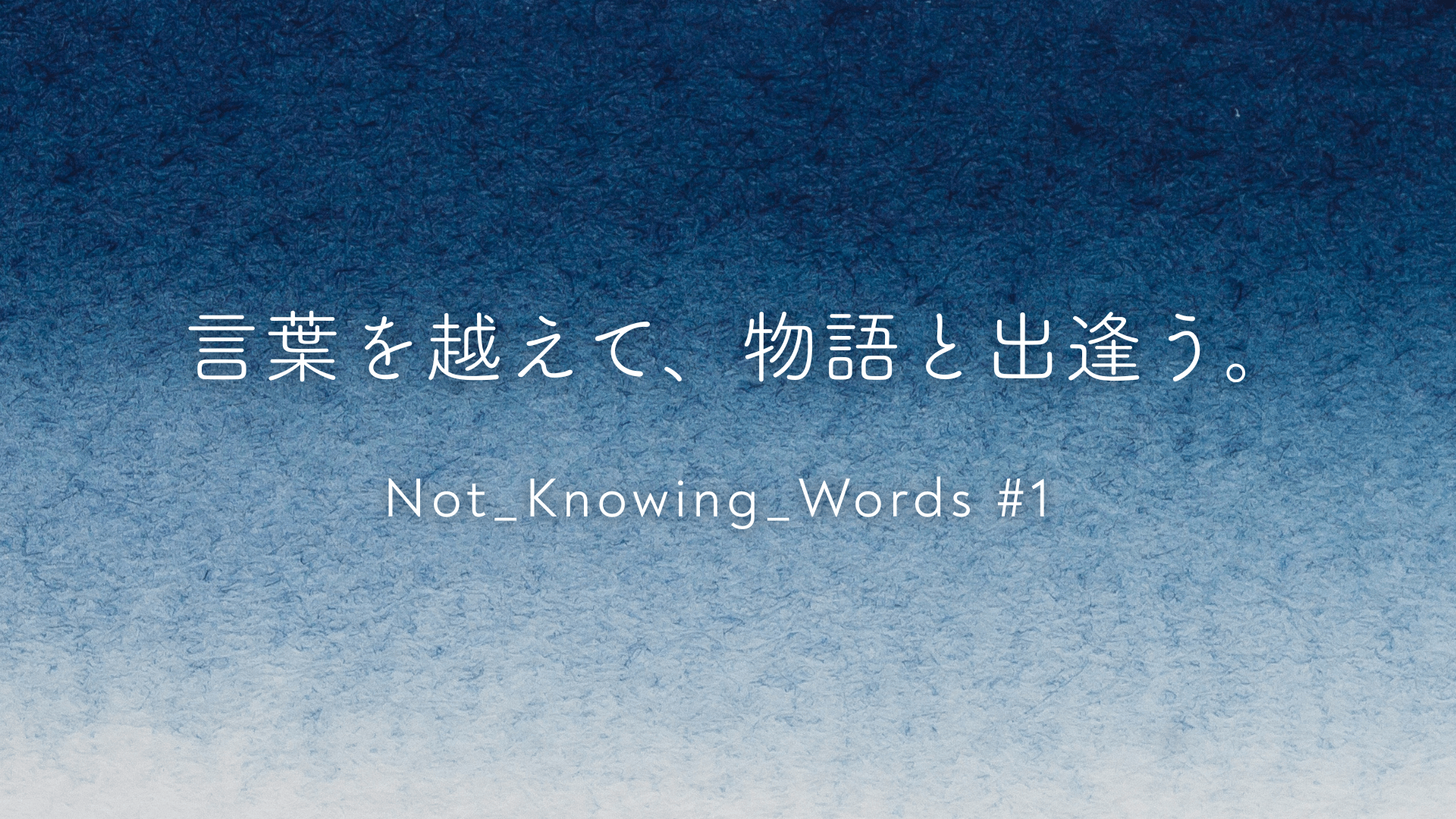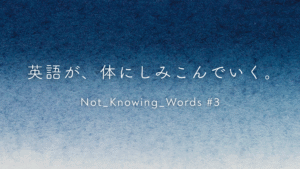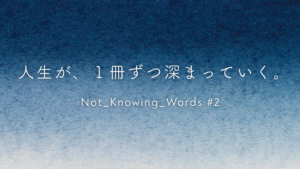今回は、ぼく自身がこれまで読んできた洋書の中から、多読初心者の方におすすめしたい 10 冊の本を紹介します。
英語学習において、多読の有用性は広く知られています。サブスクや電子書籍の普及などもあって、多読に取り組む環境はかつてないほど整ってきました。
けれど、「どんな本でも手軽に読める」という状況は一方で、「何から読めばよいか?」という迷いをもたらします。特に初心者の場合、おおまかな指針や方向性といったものが欲しくなりますよね。
本来「言葉を学ぶ」というのは “ワクワクすること” であるはずです。
例えば、フィクションを読むということは、自分ではない誰かの人生をそっとなぞること。その物語が英語で語られているだけで、見える景色が少し変わって感じられることがあります。
英語だからこそ届く感情や、英語だからこそ立ち上がってくる余韻——そうした体験は、ぼくたちの心をそっと揺らしてくれます。
これから紹介する本は、どれも英語学習者にとって取り組みやすいものですが、ただ易しいだけではありません。それぞれの本のなかに、深い学びが息づいている、あるいは心地よい読後感を味わえる、そんな物語ばかりです。
もし今、「どんな英語の本を読もうかな」と迷っている方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。
※本記事ではフィクションの洋書を紹介します。ノンフィクション編はこちらをご覧ください。
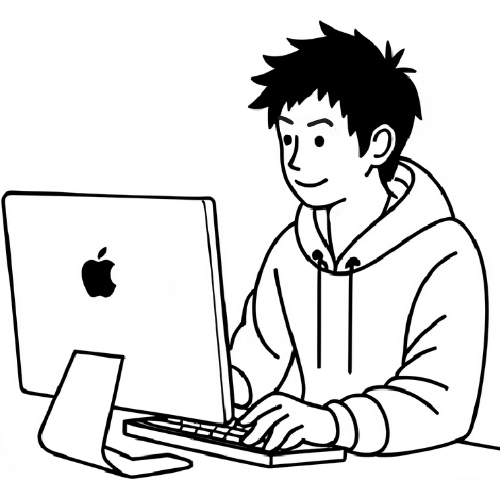
この記事を書いた人
ヒラク
NOT KNOWING JOURNAL 運営・執筆
早稲田大学 政治経済学部 政治学科
→ 総合医療機器メーカー
→ フリーランス
Short Stories in English for Beginners — 小さな成功体験を重ねる
著者 ▶ オリー・リチャーズ
肩書 ▶ 作家 / 言語教育者
分量 ▶ 240ページ
分類 ▶ 短編集
難度 ▶ ★☆☆(星1つ)
初版 ▶ 2018年
評価 ▶ ☆ 4.6(amazon)
どんな本?
『Short Stories in English for Beginners』は、「ストーリーを通じた語学学習」を提唱する著者が、英語を第二言語として学ぶ方向けに作成した短編集です。オリジナルのストーリーが 10 本程度収録されており、日常生活やちょっとした冒険を題材にした、親しみやすい内容となっています。
文章は非常にシンプルで、基本的な文法と語彙を中心に構成されており、初心者でもストレスなく読み進められるよう設計されています。
各ストーリーにはそれぞれ 単語リスト や 理解度チェック も付いており、「読む」「理解する」「暗記する」を自然な形で繰り返すことのできるサイクル になっている点も特徴です。
長編に挑戦する前の「ウォーミングアップ」にぴったりの一冊で、1話が短いため、スキマ時間に読めるのも魅力 です。英語の多読をこれから始める方に、最初の一歩としておすすめできる書籍です。
この本から得られること
✅ 短くても「完結する物語」を英語で読み通す達成感
✅ 繰り返し出てくる語彙や表現で、自然と英語に慣れる感覚
✅ 英語の語順やリズムに耳と目を慣らすトレーニング
✅ 長編に進む前の“読解筋力”づくり
✅ 英語学習のハードルを下げ、自信を育むきっかけ
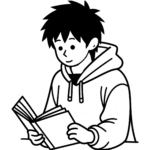 ヒラク
ヒラク英語学習を「学び」から「楽しみ」へと変えてくれる導入書。勉強という意識を捨てて、純粋に楽しんでみましょう!
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
Charlotte’s Web — 優しくも深い命の物語
著者 ▶ E・B・ホワイト
肩書 ▶ 児童文学作家
分量 ▶ 260ページ
分類 ▶ 児童文学
難度 ▶ ★☆☆(星1つ)
初版 ▶ 1952年
評価 ▶ ☆ 4.8(amazon)
どんな本?
『Charlotte’s Web(シャーロットのおくりもの)』は、子ブタのウィルバーと、知恵あるクモのシャーロットとの友情を描いた物語。見た目はシンプルな児童書ですが、その中には命の尊さや、誰かのために行動する勇気が静かに込められています。
文章は全体的にやさしく、短くて読みやすい英文が多め。特に多読を始めたばかりの人にとっては、「英語でも物語ってこんなに楽しく読めるんだ」と感じられる一冊だと思います。書籍情報サイト Goodreads では「死ぬまでに読みたい100冊の本」に認定されています。
牧場を舞台にした素朴な雰囲気、ちょっととぼけた登場人物たち、そして何よりシャーロットの “言葉の力” 。英語の読書に不安がある人でも、ページをめくる手が止まらなくなるはずです。
この本から得られること
✅ 英語で「優しい物語」に触れるよろこび
✅ 自然で豊かな語彙、会話表現に親しむ
✅ 命や友情という普遍的なテーマに英語で触れる経験
✅ 読み終えた後に残る、静かで深い感動
✅ 繊細な描写から英語のニュアンスを感じ取る力



静かな余韻を残す物語。児童書でありながら、大人の心を揺さぶるメッセージ性があります。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse — やさしい言葉に触れる
著者 ▶ チャーリー・マッケジー
肩書 ▶ 作家 / 画家
分量 ▶ 128ページ
分類 ▶ 寓話
難度 ▶ ★☆☆(星1つ)
初版 ▶ 2019年
評価 ▶ ☆ 4.8 (amazon)
どんな本?
『The Boy, the Mole, the Fox and the Horse』は、イギリスの作家・チャーリー・マッケジーによる絵本仕立ての作品。文字通り、少年・モグラ・キツネ・馬 という4つのキャラクターが登場し、彼らのシンプルで深い対話を通して、「生きること」「ありのままでいること」「優しさとはなにか」といった、根源的なテーマが描かれます。
物語にはストーリーのような起伏はなく、ページごとに詩のような短い言葉が綴られ、温かみのあるイラストとともに読む人の心にそっと寄り添います。英語のレベルとしては初級~中級程度で、シンプルな文体と短い文章の構成から、英語学習者の多読入門書としても人気があります。
単に、「やさしい英語=簡単に理解できる内容」ではなく、その言葉の奥に宿る感情や哲学的な含意 を味わえることが、この本の醍醐味です。
この本から得られること
✅ シンプルな英語で表現される、深い人生の洞察
✅「やさしい言葉」の力に触れ、自分の心を見つめ直すきっかけ
✅ 詩のような対話で英語のリズムや余韻を感じ取る
✅ 絵と文の融合によって、英語表現が直感的に理解できる
✅ 英語学習において「読む」ことの内面的な意味を再発見できる



ページをめくるたび、誰かの言葉にそっと背中を押される。そんな静かな読書体験を味わえるはず。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
Because of Winn-Dixie — 出会いが紡ぐ、心の再生の物語
著者 ▶ ケイト・ディカミロ
肩書 ▶ 児童文学作家
分量 ▶ 193ページ
分類 ▶ 児童文学
難度 ▶ ★☆☆(星1つ)
初版 ▶ 2000年
評価 ▶ ☆ 4.7 (amazon)
どんな本?
『Because of Winn-Dixie』は、アメリカの児童文学作家 ケイト・ディカミロのデビュー作で、世代を超えて愛される名作です。タイトルの「ウィン・ディキシー」とは、物語の鍵を握る一匹の犬の名前。彼との出会いが、少女と周囲の人々の心に変化をもたらしていきます。
主人公は10歳の少女 オパール 。母親が家を出て以来、父とともに新しい町へ引っ越してきたばかりのオパールは、孤独と向き合いながら新しい生活に馴染もうとしています。ある日スーパーマーケットで騒ぎを起こした犬を「ウィン・ディキシー」と名づけて家に連れ帰ることで、彼女の日常が少しずつ色づき始めます。
文章は比較的平易ですが、リズミカルで生き生きとした語り口、登場人物の自然な会話が、読解力と表現力 を育てるのに役立ちます。
この本から得られること
✅ シンプルな英語で綴られた、感情豊かな語りを味わえる
✅ “つながり”や“共感”といったテーマに触れ、内面的な気づきを得られる
✅ 人との関係を育む会話表現や心の動きにまつわる英語表現を学べる
✅ 英語を「ただ理解する」以上に、「感じながら読む」経験を積める
✅ 自然な文章に慣れながら、物語を通じて読解力を育てられる



読後には、小さな灯火がそっと胸に灯るような温かさがあります。英語表現の豊かさを味わえる1冊ですよ。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
Out of My Mind — 声なき声が、世界を変えていく
著者 ▶ シャロン・ドレーパー
肩書 ▶ 作家
分量 ▶ 301ページ
分類 ▶ 児童文学
難度 ▶ ★★☆(星2つ)
初版 ▶ 2010年
評価 ▶ ☆ 4.7(amazon)
どんな本?
『Out of My Mind』 は、米国の作家シャロン・ドレーパー によって書かれた児童文学作品で、言葉を話すことができない少女が、自分の「思い」を世界に届けようとする物語です。
主人公は、重度の脳性まひをもつ11歳の少女・メロディ。彼女の身体は思うように動かず、言葉を発することもできません。けれども、彼女の心の中には、美しい言葉、鋭い知性、そして世界への熱いまなざし が満ちています。
学校では「何もわからない子」と誤解され、周囲の子どもたちにも受け入れられない日々。けれど、あるきっかけを通じて、メロディは「言葉を発するための道具」を手にし、少しずつ自分を表現する道を切り開いていきます。
この本から得られること
✅ 声にならない思いに耳を澄ます力
✅ 共感力を育てる繊細な読書体験
✅ 感情表現に富んだ英語の語彙力
✅ 優しいまなざしで偏見を見つめ直す視点
✅ ことばの重みを再発見する気づき
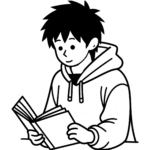
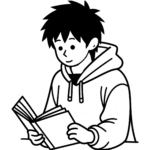
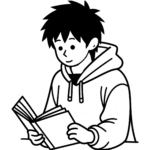
人間の持つ強さ、可能性を再認識させられる1冊。物語の最後に起こる出来事にも、いろいろと考えさせられるものがあります。
Holes — 伏線がつながる快感
著者 ▶ ルイス・サッカー
肩書 ▶ 児童文学作家
分量 ▶ 241ページ
分類 ▶ ヤングアダルト
難度 ▶ ★★☆(星2つ)
初版 ▶ 1998年
評価 ▶ ☆ 4.4(amazon)
どんな本?
『Holes』はアメリカの作家ルイス・サッカーによる児童向け小説で、数々の文学賞を受賞しています。子ども向けの作品でありながら、大人も惹きこまれるほどの構成の巧みさと奥深さを持ち、世界中で読み継がれている傑作です。
物語の主人公は、冤罪により「少年更生キャンプ」へ送られた少年 スタンリー・イェルナッツ。
キャンプでは、毎日ひたすら砂漠に穴を掘る作業を課せられます。「人格形成のため」とされているその作業ですが、やがてそれが実は “何かを探すため” のものだと分かってきます。
物語は、スタンリーの現在と、彼の祖先の過去、さらにキャンプ地で起きた百年前の出来事 が交錯しながら展開し、やがて一つの点に収束していきます。その巧妙なストーリーテリングと、ユーモア、皮肉、友情、勇気が織りなす物語に、読む手が止まらなくなるはずです。
この本から得られること
✅ 伏線と因果関係を読み解く読解力
✅ アメリカ英語のカジュアルな語感
✅ 過去と現在をつなげて読む想像力
✅ 理不尽な状況下でも希望を失わない強さ
✅ 英語で物語を「楽しむ」感覚の第一歩



「穴を掘る」ことの意味が、読後に大きな余韻を残す。運命が交錯するストーリーはきっと、心に残る読書体験になるでしょう。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
The Giver — 完璧な世界への問い
著者 ▶ ロイス・ローリー
肩書 ▶ 児童文学作家
分量 ▶ 256ページ(ペーパーバック)
分類 ▶ SF・ディストピア
難度 ▶ ★★☆(星2つ)
初版 ▶ 1993年
評価 ▶ ☆ 4.6(amazon)
どんな本?
『The Giver』はアメリカの作家 ロイス・ローリーによって出版された、ディストピア小説です。全米図書賞やニューベリー賞を受賞しており、英語圏では学校教材にも採用されるなど、多くの読者に愛されてきた現代の古典とも言える1冊。
舞台は「痛み」も「争い」も「色」さえも存在しない、完全に管理された社会。人々は感情を抑制され、記憶を持たず、「同じ」であることによって安定を保っています。
そんな世界で12歳になった主人公 ジョナス は、「記憶を受け継ぐ者」という特別な役割に選ばれます。そして、前任者から、過去の記憶——人類の喜び、痛み、色彩、音楽、愛といったあらゆる感情や経験を受け取っていくのです。
物語は淡々とした語り口で進みますが、ジョナスが初めて「雪」や「音楽」や「死」を体験していく描写は、新鮮な感動を伴います。物語が進むにつれ、読者は彼の目を通して、自由とは何か、幸せとは何か、そして「管理された平和」の裏にあるもの を考えさせられます。
この本から得られること
✅ 象徴を読み取る読解力
✅ 感情や抽象概念の表現に親しむ語彙力
✅ ディストピア小説の構造理解
✅「自由」や「個性」について考えるきっかけ
✅ 英語で哲学的なテーマを味わう体験



色も感情も“奪われた世界”のなかで、初めて世界の輪郭が見えてくる—。「考える読書」へと、そっと扉をひらいてくれる1冊です。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
The Storied Life of A. J. Fikry — 本とともに、人生はひらかれる
著者 ▶ ガブリエル・ゼヴィン
肩書 ▶ 作家 / 脚本家
分量 ▶ 273ページ
分類 ▶ ヒューマンノベル
難度 ▶ ★★☆(星2つ)
初版 ▶ 2014年
評価 ▶ ☆ 4.3(amazon)
どんな本?
『The Storied Life of A. J. Fikry』は、アメリカの作家ガブリエル・ゼヴィンによるヒューマンノベル。
舞台は小さな島にある書店「アイランド・ブックス」。主人公のA・J・フィクリーは、偏屈で皮肉屋な中年の書店主で、妻を亡くしてからというもの、人との関わりを避け、読書だけを心の拠り所にしています。
そんな彼のもとに、ある日突然、幼い女の子が「あなたに育ててほしい」という手紙とともに店に置き去りにされます。最初は戸惑いながらも、その子どもとの出会いがフィクリーの人生に少しずつ変化をもたらし、彼は本を通じて人と繋がる喜びを取り戻していきます。
随所に実在の文学作品や短編小説への言及がちりばめられており、文学への愛情があふれる一冊です。
それでいて、語り口は軽やかでユーモラス。シリアスなテーマも、優しさで包まれており、大人の読者がくすっと笑いながらも、胸の奥にじんわりと余韻を残すような仕上がり になっています。
この本から得られること
✅ 日常的な会話表現や自然な英語のリズム
✅ 読書にまつわる語彙や文学的引用
✅ ユーモアと感傷を行き来する語調への理解
✅ 人間関係の繊細な描写に触れる読解力
✅ 本が人生を支える力について考える視点
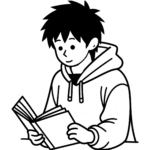
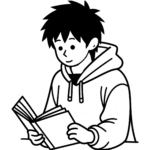
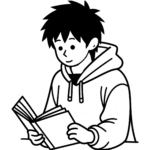
個人的にお気に入りの1冊。優しさに満ちたストーリーは、言葉の力と人生のあたたかさを静かに伝えてくれます。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
The Old Man and the Sea — 静かな海に宿る、誇りと孤独の物語
著者 ▶ アーネスト・ヘミングウェイ
肩書 ▶ 作家
頁数 ▶ 108ページ
分類 ▶ 純文学
難度 ▶ ★★★(星3つ)
初版 ▶ 1952年
評価 ▶ ☆ 4.4 (amazon)
どんな本?
『The Old Man and the Sea』は、アメリカの作家 アーネスト・ヘミングウェイによる短編小説で、1952年に発表されました。ヘミングウェイがノーベル文学賞を受賞する決め手となった作品でもあります。
物語の舞台はキューバ沖の海。主人公は、84日間魚が一匹も釣れずにいる老漁師・サンチャゴ。彼は「運に見放された老人」として村の人々にささやかれています。
しかし、老いた身体を押して沖へと漕ぎ出し、ついに巨大なカジキと出会う。数日間にわたる孤独な闘いの末に、彼が得たものとは——。
文章は非常に簡潔で、短くリズムのよい文が連なります。使われている語彙も平易で、会話文と描写がバランスよく織り交ぜられているため、英語多読初心者でも取り組みやすい一冊 です。
この本から得られること
✅ シンプルな英語で語られる深いテーマへの読解力
✅ 自然や孤独、人間の尊厳に関する内省的な視点
✅ 余白の多い表現から行間を読む力
✅「敗北しながら勝つ」という逆説的な価値観の理解
✅ 英語で文学を読む醍醐味に触れる体験



漁師サンチャゴの姿に、自分自身の闘いを重ねながら読む——そんな読書体験のできる一冊です。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
The Alchemist — 夢を追う巡礼の旅
著者 ▶ パウロ・コエーリョ
肩書 ▶ 作詞家 / 小説家
分量 ▶ 213ページ
分類 ▶ 寓話
難度 ▶ ★★★(星3つ)
初版 ▶ 1988年
評価 ▶ ☆ 4.5 (amazon)
どんな本?
『The Alchemist』は、ブラジルの作家 パウロ・コエーリョによって書かれた、世界的ベストセラーの1冊。
スペイン・アンダルシアの羊飼いの少年・サンチャゴが、ある夜見た「エジプトのピラミッドに宝物がある」という夢に導かれて旅に出る——そんなシンプルな筋書きの中に、深い人生のメッセージ が織り込まれています。
物語は、サンチャゴの旅路を描きながら、誰もが持つ “自分の使命” を探す旅へと読者を誘います。旅の途中で出会う人物たちとの対話を通して、彼は自分の内なる声に耳を傾けることを学びます。
短く簡潔な英語で綴られており、哲学的なテーマを扱いながらも読みにくさは感じさせません。むしろ、詩のようにリズムのある言葉遣いが、静かな読書体験へと導いてくれます。
この本から得られること
✅ シンプルながら深い哲学的表現に触れる力
✅ 夢や運命について英語で考えるきっかけ
✅ 寓話の形で英語を楽しむ読解力
✅ 抽象的概念を理解する語彙力
✅ 人生の旅を英語で味わう体験



シンプルな言葉の中に深い想いが詰まった内容。自分の人生に思いを寄せながら読むと、深い読書体験が得られるはず。
👉 SafariでAmazonページがうまく開けない方はこちら。
—— たくさんの本に出会っていくには、電子書籍というかたちもひとつの選択肢かもしれません。
特に Amazon Kindle Unlimited では、さまざまな英語の物語に月額で触れることができます。
ぼく自身もこのサービスを使って読書の幅が大きく広がりました。
初心者が英語多読に取り組むうえで注意したい3つのこと
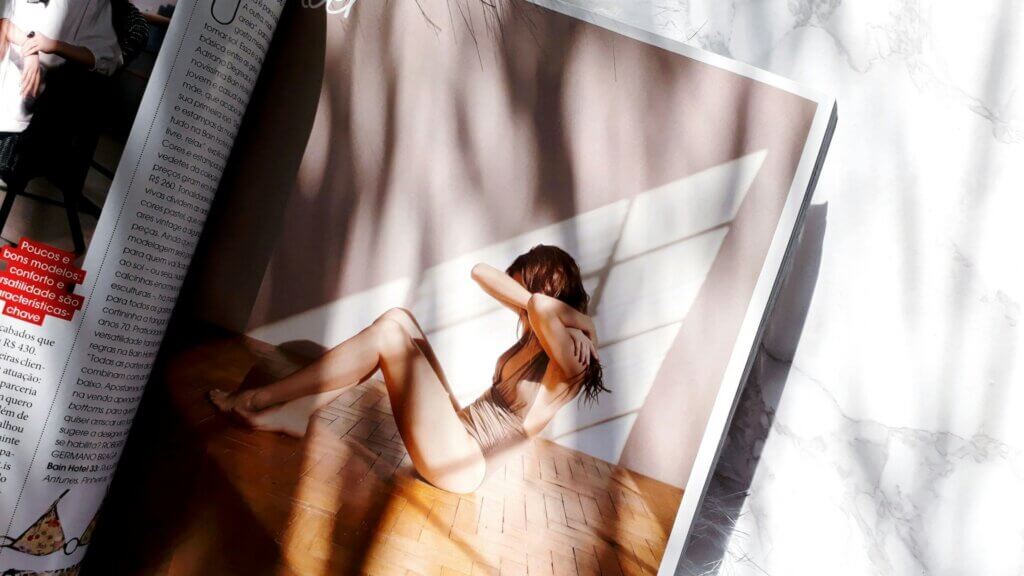
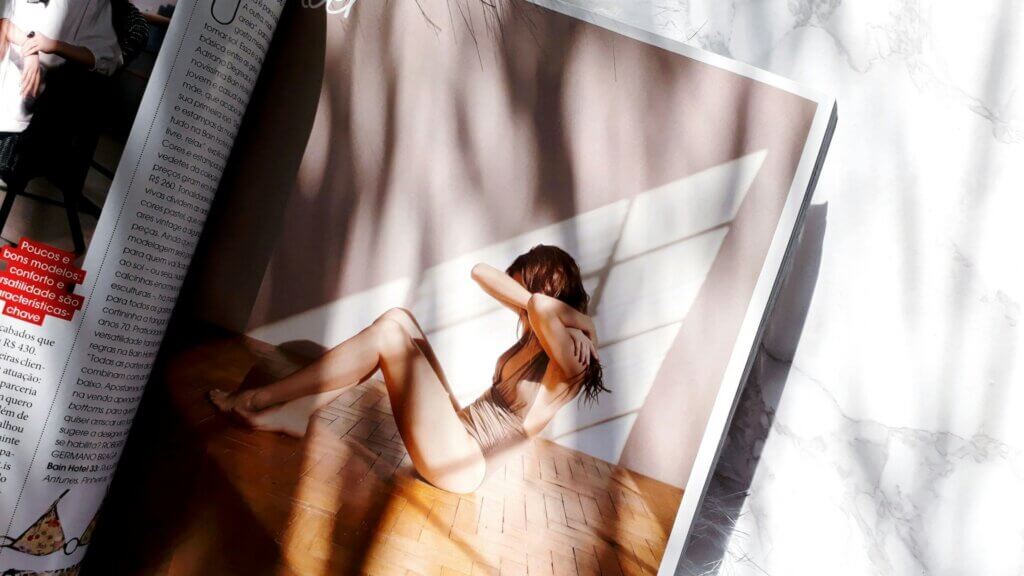
多読に取り組むうえで、注意したいポイントは以下の3つです。
難易度の高い本にもチャレンジする
多読に対する取り組み方としてあなたに提案したいのは、「難易度の高い本にもチャレンジしましょう」ということです。それは、多読の目的である「パターン認識」のためです。
英文のパターンを脳に落とし込むには、「たくさん読む」だけでなく、さまざまなレベル・ジャンルの英文に触れる必要があります。特に注意したいのが「レベル(難易度)」です。
初心者だからと言って、いつまでも簡単な英文にしか触れないでいると、多読がもたらす「パターン認識」の効果を得ることにつながりません。
個人的に、多読の学習効果を最大化するコツは「自分の英語レベルよりワンランク上の英文に触れること」だと思っています。「単語学習」や「精読学習」でインストールした英語の基礎力。その基礎力をアップデートするうえで最適なのが「多読」です。
インストール段階では自分の英語レベルに合ったものを読むのが良いですが、アップデート段階ではある程度高い負荷をかける必要 があります。ひとつ上のレベルに進むには、実際にそのレベルにあるものに触れなければなりませんよね。
実際に翻訳者として活躍する橋本大也さんは著書の中で、「インプット仮説」という学説を紹介しています。インプット仮説 のポイントは、以下の2点です。
- 言語力向上に必要なのは、大量の言葉を読むこと・聴くこと(インプット)である。
- 学習者が理解可能なレベル( i )より、ほんの少しだけ高いレベルのインプット( i + 1 )を大量に受けるのが最も効果的。
その上で、橋本さんは「 i + 1 のインプットを受け続ける環境を作ることができれば、英語は必ず上達する」と断言しています。
こうした点を踏まえると、英文のレベルに制限を設けていては「多読」の効果が半減してしまうことはわかってもらえるはず。読書の楽しさが損なわれない範囲で、難しい本にもチャレンジしてみましょう。
勉強という意識を捨てる
次に提案したいのは、「勉強という意識を捨てる」ということです。あまり難しいことを考えずに、娯楽感覚で取り組むことが大切だと思います。
ボクは今でも多読を続けていますが、自分の「読みたい」を最優先にしていますし、飽きたら読むのをやめるということもよくあります。NETFLIXで見始めたドラマがつまらなくて途中でやめるのと同じ感覚です。娯楽なのでそれでいいと思っています。
不思議なもので、同じ「多読」であっても“勉強”という意識が働くと途端に息苦しくなってしまいます。
「気楽に本を手にとり、好きなものだけ読み進める」「途中でやめても罪悪感を感じる必要はない」ということを意識して取り組むことをおすすめします。
多読がすべてではない
さらに、もうひとつあなたに提案したいのは「『多読』がすべてではない」ということです。通常、多読においては辞書を使わずに読み進め、おおまかに理解できれば OK とされています。
ですがこれはあくまでも「多読」でのハナシ。当然ですが、英語力アップのための学習法は「多読」だけに限りません。
本の難易度やあなたの興味に応じて、時には辞書を使ってじっくり読み進めるのもよいでしょう。ボクは 正確な理解が求められる本(仕事関係・お金関係)や じっくり読みたい本 は必要に応じて辞書を使います。
英語の学び直しに取り組み始めたころは今よりも英語力が低かったので、【 フィクション → 辞書を使う 】【 ノンフィクション → 辞書を使わない 】といった感じで、ジャンルごとに読み方を使い分けていました。フィクションはわからない箇所があるとストーリーを追えなくなってしまうからです。
時として辞書を使いながらじっくり読み進めるのも、それはそれで楽しいもの。
日本人はマジメだから、「辞書を使ってはいけません」「自分のレベルに合った本だけ読みましょう」と言われると、言われたとおりにやってしまいます。
ですが、勉強の醍醐味は自分でアレコレ考えながら、時には遠回りしながら、自分オリジナルの学習法を自分自身で発見していくことにあると思います。「多読」は英語学習におけるひとつの選択肢に過ぎないということを頭に入れたうえで、自分にピッタリ当てはまる学習バランスを見極めるとよいでしょう。
まとめ — 多読に向き合う、勇気ある一歩を


冒頭で話したように、日本人の英語学習者はどうしても「正しい取り組み方」にとらわれてしまいます。
「正解」を追い求め、最短距離で効率よく学習しなければならないと思い込んでいるのです。
その強迫観念から、「理解できなければ意味がない」と考えてしまい、多読においても、いつまでも簡単な本にしか手を出さない状況に陥ってしまうのでしょう。
ですが、ぼくは「たくさんの “わからない” に出会うこと」が学びの本質だと考えています。
「わからない」の世界にどっぷりと身を浸しているうちに、ぼんやりと “英語の輪郭” が見えてくるのです。
少しだけ背伸びをして、普段は読まないような本に挑戦してみる。
その勇気ある一歩が、言葉の世界を広げ、理解を深め、知らなかった自分を見つける旅へとつながります。
今回ご紹介した 10 冊は、どれも読みやすさと深みのバランスを考え抜いて選びました。
どうか恐れずに、でも焦らずに、自分のペースで歩んでいってください。
多読は単なる学習法ではなく、未知の景色を求める旅路。
新しい世界への扉を一つずつ、あなた自身の手で開いていくための道しるべとなれば幸いです。
📬 ことばが、どこかであなたに触れたなら──
小さな便りをお寄せいただけたら、とても励みになります。