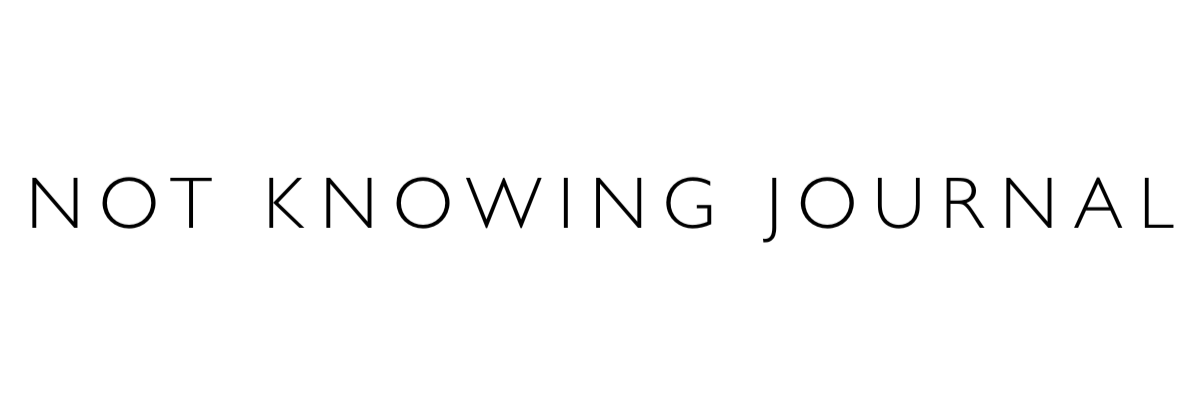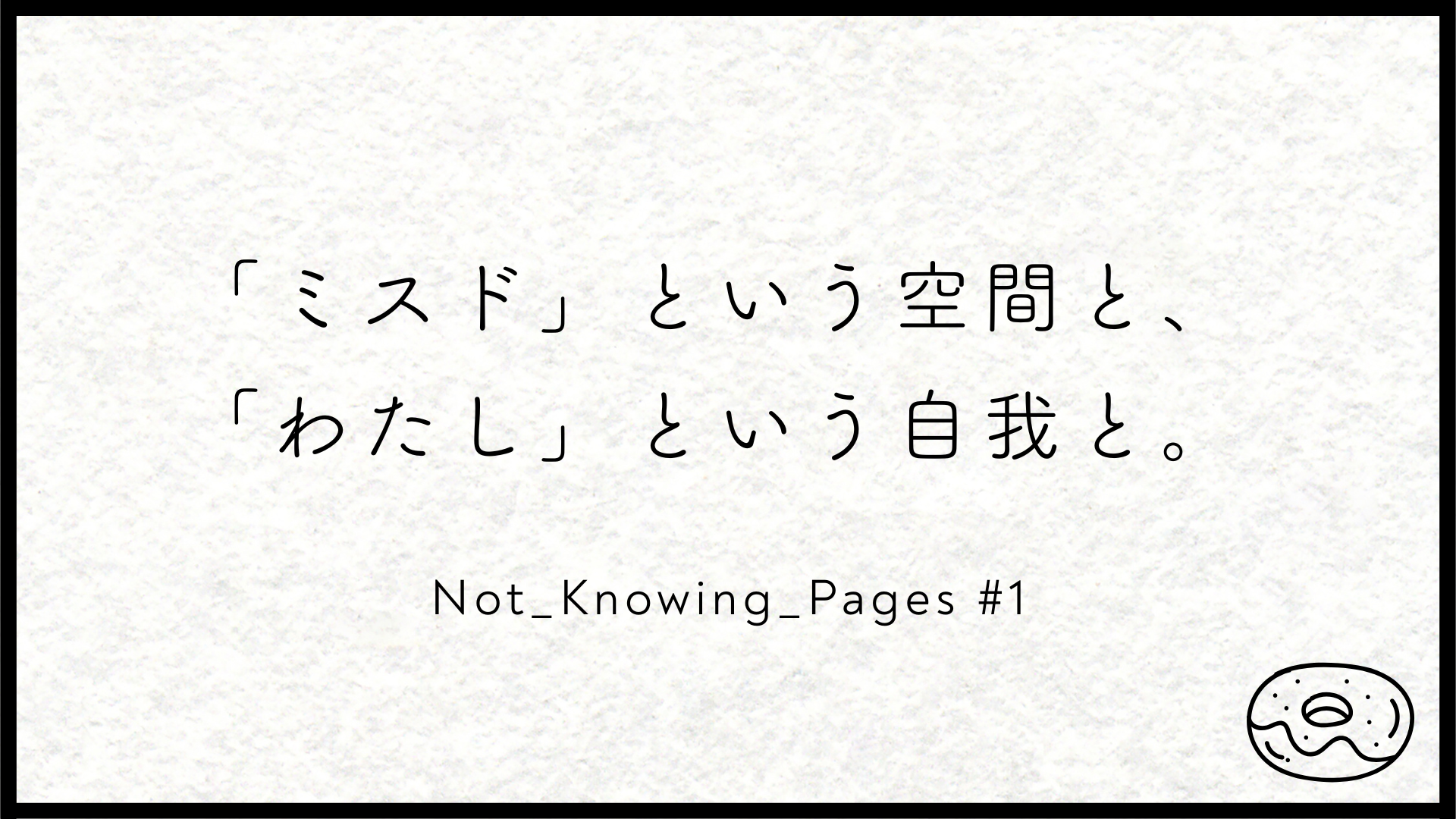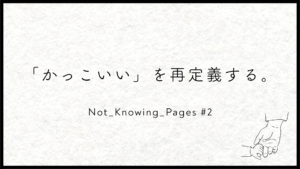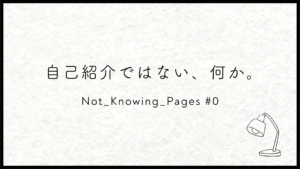ぼくは、ミスドに入ったことがない。
甘い香りに包まれたあの空間を、
ただの一度も、体験したことがない。
いや、前を通ったことは何度もある。
人々がたくさんのドーナツの前で悩んでいる様子も、よく知っている。
なのに、なぜか一歩が踏み出せない。
理由は、いくつかある。
注文の仕方がわからない。
お会計のタイミングもよくわからない。
セルフなの? それとも店員さんが取ってくれるの?
──そんな不安が頭をよぎるたび、僕はそっと通り過ぎてきた。
でも、それだけじゃない。
最大の理由は、たぶんこれだ。
「ぼくの顔が昭和すぎて、ミスドの世界観を壊してしまいそうだから。」
ぼくの顔は昭和という古き良き時代を体現している。
平成生まれなのに、である。
昭和の銀幕スターのプロマイドの中に、ぼくの顔写真を混ぜても、何の違和感もない。
高倉健がミスドにいてはダメだろう。菅原文太もいちゃダメだ。
だから、ぼくもいちゃダメなのだ。
ぼくがミスドに入ってしまえば、ママと一緒にやってきた子供が泣いてしまうかもしれない。
学校帰りの女子高生たちが恐怖におののくかもしれない。
そして、何よりミスドの株価が大暴落してしまうに違いない。
だから今日も、ボクはミスドの前を素通りする。
「ドーナツなんか興味ありませんよ」という顔をして。
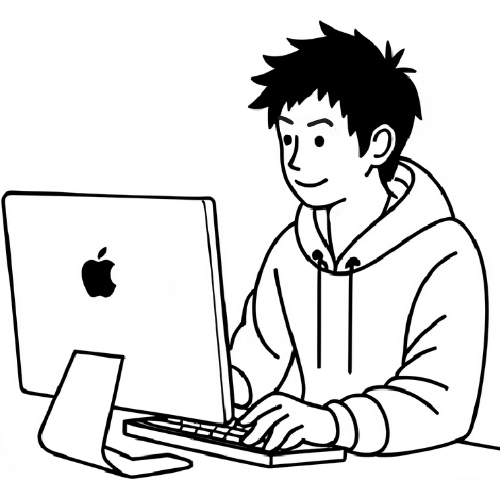
この記事を書いた人
ヒラク
NOT KNOWING JOURNAL 運営・執筆
早稲田大学 政治経済学部 政治学科
→ 総合医療機器メーカー
→ フリーランス
ぼくはなぜ、ミスドに入れなかったのか?

注文の仕方がわからない不安
ミスタードーナツって、どうやって注文するんだろう──
それがずっと、わからない。
ドーナツって、あのガラス(ショーケース?)の向こうにずらっと並んでるじゃないですか。
まず、トレイを取るのか? トングを使うのか?
それとも、店員さんに「これください」って言うシステムなのか?
自分なりにシミュレーションをしてみたこともある。
でも、どうしても自分がそこに混ざれる気がしない。
「自分ひとりだけ、やたらモタついたらどうしよう」
「後ろに並んでる人にイラつかれたらどうしよう」
そんな妄想ばかりが頭をよぎって、結局、足がすくんでしまう。
あと、「レジに持ってくまでの距離感」も恐ろしい。
あの、広い空間。あの沈黙。
ドーナツを持った昭和顔の男が、若いママさんや女子高生たちと同じ空間を占める。
もはや、悲劇である。どんな名監督も映像化できない悲劇が、そこにある。
しかも、なんかミスドの店員さんって、キラキラしてるイメージがあるじゃないですか。(入ったことないから知らんけど)
あーいうところで働いてる子は、笑顔がまぶしい。直視できない。
そんな中に、昭和な顔した男がひとり、オロオロと立っていたら…
やっぱり、どう転んでも悲劇だ。どんな名監督も映像化できない悲劇が、そこにある(2回目)。
そう思うと、今日もミスドの扉の前を素通りしてしまう。
「買い方がわからない」というのは、
ほんの小さなことかもしれないけど、
ぼくにとっては、それが立ち入りをためらう理由のひとつになっている。
昭和顔の男がポン・デ・リングを貪る地獄絵図
想像してみてほしい。
明るくて、カラフルなミスタードーナツの店内。
壁にはポン・デ・ライオンのイラストが笑い、
女子高生たちが楽しそうにドーナツを選んでいる。
その隣で、無表情の昭和顔がポン・デ・リングを食べている。喰らっている。貪(むさぼ)っている。
想像するだけで、恐ろしい。
まるで漫画のように、その場の空気が凍りつくかもしれない。
ミスドは、ふんわり甘い夢の世界である。
その世界で、昭和顔の男がドーナツをふがふが言いながら喰らっている姿は、
そこにいるみんなの楽しい時間を壊してしまいそうで怖い。
実際、誰かに拒絶されたわけではない。
だが、自分の中の直感が言う。「ここはおまえの居場所じゃない」と。
そんな気持ちが、店の前で立ち止まる理由だ。
ポン・デ・リングはとても美味しそうだ。
ただ、ぼくにはその世界に足を踏み入れる勇気がない。
“顔が昭和”ゆえに立ち入れない場所たち

サーティワン・サンリオショップ・ディズニーランド etc …
ミスタードーナツだけではない。
他にも、「顔が昭和」ゆえに近づきにくい場所がいくつかある。
たとえば、サーティワンアイスクリーム の店舗。
カラフルなアイスがずらりと並び、子どもや若いカップルでにぎわう場所だ。
以前、お付き合いしていた子が大のサーティワン好きだったが、一緒に行くことはなかった。
彼女も日本兵みたいな顔した男を連れていくことに、ささやかな抵抗感を抱いていたのだろう。
サンリオショップ も同様である。
キティちゃんやマイメロディ、ポムポムプリンたちのかわいらしい世界。
まるで絵本の中の一場面のようなその空間に、
三島由紀夫本人よりも三島由紀夫っぽい顔が混じることは許されない。
そして、言わずもがな、ディズニーランド 。
夢と魔法の王国は、笑顔ときらめきとファンタジーに満ちている。
ここに昭和顔の男がふらりと現れたら、魔法が消えてしまうのではないか。
ウォルト・ディズニーの理念を、根本から覆しかねない。
もちろん、これはすべて自意識の産物である。
誰かに直接拒まれたわけではない。
ただ、自分の中の直感がそう告げているだけだ。
これらの場所は、ぼくにとっては遠い世界のままだ。
近づこうとするたびに、なぜか一歩引いてしまう。
それが、「顔が昭和」というものの持つ、地味だけれど強い呪縛なのかもしれない。
入れないのは店舗じゃなく、“世界観”なのかもしれない
入れなかったのは、店舗じゃなくて、「世界観」なのだろう。
というのも、ミスドもサーティワンもサンリオも、ただの店じゃない。そこにはそれぞれの “空気感” みたいなものがある。
明るくて、キラキラしてて、カラフルで、なんだか全部が軽やかだ。
そういう雰囲気に、自分はあまりにも似合わなさすぎると思ってしまうのだ。
あの空間に立った自分の姿を想像すると、とにかく場違いな気がしてしまう。
ミスドのカウンターの前に、昭和顔のおじさんが立っていたら、世界観が歪む気がしてならない。
ポン・デ・リングのふわふわと、昭和のごつごつは、共存できないのだ。
でも考えてみれば、これは別に顔の問題だけじゃない。
「自分にはあの空間に入る資格がない」とか、「似合わない」みたいな感覚。
それって、劣等感であると同時に、“距離感” だとも言える。
世界と自分との間に、なんとなく距離を感じてしまうのだ。
ただ、それって別に悪いことじゃない気もしている。
“劣等感” という認識を “距離感” へと変換するだけで、「自分の居場所は別にあるかも」って思えるからだ。
ミスドの前を素通りするたびに、なぜかちょっと人生のことを考えたりするのも、そのおかげかもしれない。
つまり、ぼくにとっては「入れない」という体験そのものが、ひとつの問いになっていた。
ミスドと自分を隔てる壁の前で、「自分が生きていく世界って、どこにあるんだろう」と、そんなことばかり考えてきたのだ。
空気に負けて、生きる

劣等感との付き合い方
かつては、「持っている人」を羨ましく思ったこともあった。
お金があって、顔が整っていて、流行の服を着て、おしゃれなカフェに自然と溶け込めるような人たちを見ては、自分はなんて冴えないんだろう、と。
大学に入ってすぐ、父が亡くなった。
仕送りに頼ることなく生きていくために、ぼくの大学生活はバイト三昧だった。
周りのみんなは、週末ごとに飲み会だの合コンだのと、楽しいキャンパスライフを送っている。
一方のぼくは、学校までの電車賃も出せない日があった。
浪人してまで入った大学で、ぼくは勉強もできず、遊ぶこともできず、ただただ働いていた。
自分がみじめで、恥ずかしくて、哀れだった。劣った存在だと思っていた。
その頃の世界観が、今も頭から離れないのかもしれない。
“自分” と “みんな” との間に線を引く癖。“自分” と “華やかな世界” を遠ざける癖。
その癖は今も治らないけれど、世界を「上下」とか「優劣」ではない関係性でとらえられるようになってきた。
「ない」ことに悩み、「ある」人に嫉妬する日々を経て、今は「持っていない生活」の中に、しみじみとした豊かさを感じている。
食べるものは自分でつくる。服は気に入った一着を長く着る。
静かな時間を大切にして、本を読む。
派手なものはないけれど、心は不思議と静かで、穏やかだ。
それは、ひょっとすると──
ミスドに入れなかったおかげかもしれない。
あのカラフルで甘い夢の国のような空間に、足を踏み入れられなかったからこそ、ボクは「自分にとっての心地よさ」を探すようになった。
キラキラしたドーナツより手づくりのおにぎりのほうが、ぼくにはよく似合う。
高級スイーツより、実家の冷蔵庫にあるような素朴なゼリーが、なんだかホッとする。
たぶんぼくは、「持たないこと」で、自分らしくいられる場所を見つけてきたんだと思う。
劣等感は、まだときどき顔を出す。
だけど、それは今では、ただの“付き合いの古い友人”のような存在だ。
今日もミスドの前を通りながら思う。
「うん、行かなくてよかったかもしれない」と。
……いや、ちょっとだけ行ってみてもいいかもしれない、とも思う。
その揺れ動きが、ボクの今をつくっている。
自炊で生きていくという選択肢
そもそも、外食自体が苦手だ。
気おくれしてしまう。
というより、なんだか居場所がない感じがして、落ち着かない。
だからぼくは、自炊をする。
たいした料理じゃない。
スーパーで安く買った野菜を炒めたり、味噌汁を作ったり。
米を研いで、炊飯器のスイッチを押す。
ただそれだけ。
でも、それが案外、悪くない。
むしろ、ちょっとした幸せを感じるようになってきた。
「美味しさ」で言えば、外食にはかなわない。
だけど、みんながみんな「美味しさ」を追い求める必要もない 、とも思う。
自分で作って、自分で食べる。
誰に見せるわけでもないし、誰かに褒められるわけでもない。
でも、自分が生きてる感じはする。「生活」をしている感じがする。
これはこれで、すごく大事なことだと思う。
今のぼくには、これで充分だ。
足るを知る ってこういうことかもしれないなと思う。
今日も、何も変わらない粗末な食事。
それだけで、十分。
いや、むしろ、ありがたいくらいだ。
こんな生活を、ぼくは選んだ。
ミスドに入れなかったからこそ、見つけられたもの

ミスドに入れなかった——でも、だからこそ気づいたことがある。
ひとりで食べるごはんだって、ちゃんとあったかい。
コンビニじゃなくて、スーパーで野菜を買って、味噌汁をつくる。
鍋の蓋をあけたときの湯気とか、お米が炊ける匂いとか。
自分の中で、ちいさな幸せを感じられる時間だ。
華やかな店で食べるわけじゃない。
おしゃれな写真も撮れない。
でも、そこにはちゃんと「自分の生活」がある。
食べること、生きることに、ちょっとずつ手間ひまをかけるうちに、
「ああ、これでいいのかもしれないな」と思えるようになった。
ミスドに入れなかったから、見つけられた幸せだと思っている。
今日も、ミスドの前を通り過ぎて、夕食の食材を買いに行く。
これが、ぼくにとっての正解なのかもしれない。
📬 ことばが、どこかであなたに触れたなら──
小さな便りをお寄せいただけたら、とても励みになります。